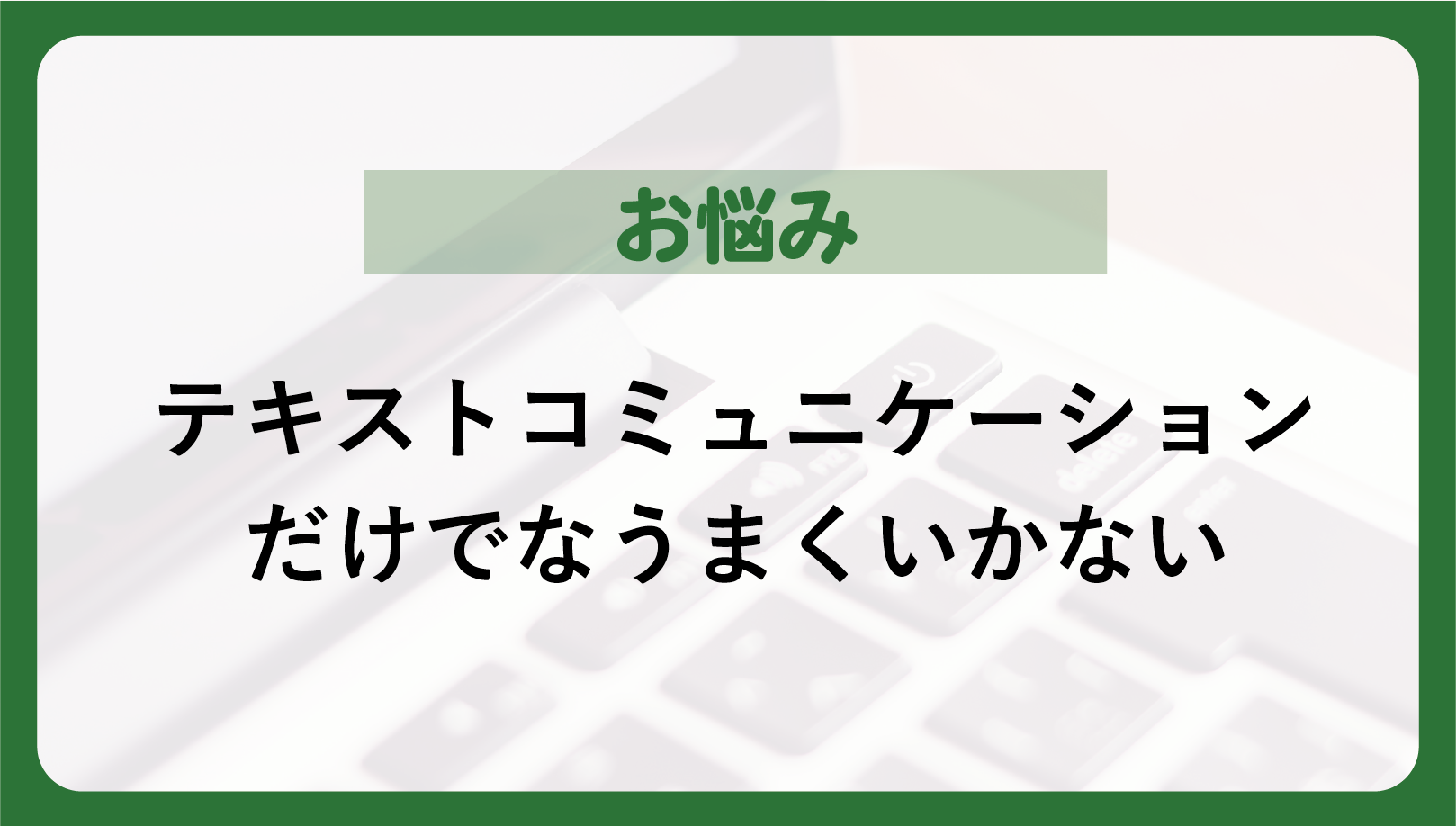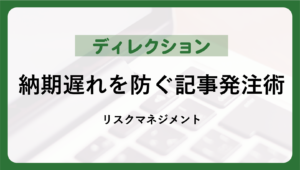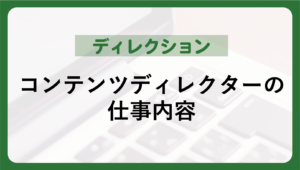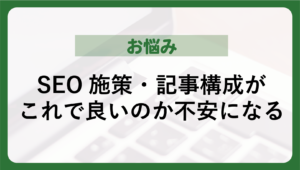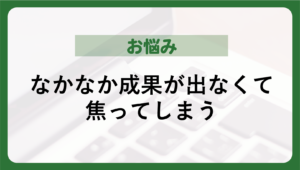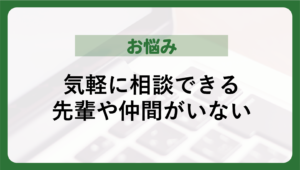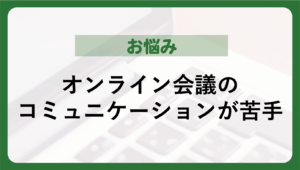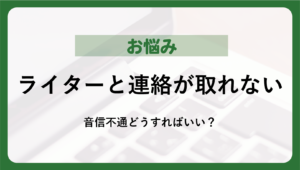クライアントやクリエイターとやりとりをする手段がチャットやメッセージのみなので、うまく理解してもらえないことがよくあり、納品物がイメージと乖離してしまうことがあります。何か対策はありませんか?
Webディレクターはチャットやメッセージのみでやりとりをする、テキストコミュニケーションでやりとりすることが非常に多いので、伝えたいことがうまく伝えられないことや、相手の言っていることがよくわからない、ということが起きがちです。
オンライン会議や対面での会議も合わせてできれば良いのですが、業務の都合上、どうしてもテキストコミュニケーションのみになってしまうことも多いと思うので、その中でもうまくやりとりをする方法を解説していきます。
相手はメッセージを正確に読まない前提でやりとりする
メッセージを送っている側としては、送った内容を全て読んでくれていると思いがちですが、相手はメッセージを正確に読んでいるとは限りません。
もし相手が、日頃からチャットが多く来る人で、常に新着通知が鳴っているような人の場合、メッセージのほとんどは流し読みになってしまい、内容を正確に理解しません。
メッセージを送る側としては、まずはこのような前提だということを認識した上でコミュニケーションを取ることが大切になります。
伝えたいことを分散させない
相手はメッセージを正確に読まないので、こちらが伝えたい内容を流し読みして、あまり重要ではない内容を重点的に読むかもしれません。
ですので、メッセージを送るときはただ殴り書きで単調な文章を送るのではなく、伝えたいことが伝わるような工夫をしましょう。
- 結論から書く
- 見出しをつける
- 強調したい箇所にかぎかっこをつける
- 改行して読みやすくする
これらを使い分けることによって、相手の反応も変わってきます。
ただし、上記の工夫を多用するのはよくありません。見出しが多すぎると結局何を伝えたいのかわからなくなりますし、かぎかっこが多すぎると何を強調したいのかわからなくなってしまいます。
相手によってメッセージの送り方も変える
相手によって送る文章の工夫の仕方も変えていきましょう。
例えば、相手が日常的に忙しい経営者の方であれば、メッセージを見るのは隙間時間になると思います。その隙間時間にチャットを開いたときに要点を伝えられるかどうかが勝負です。
一方で、日中から比較的時間が取れるライターやクリエイターであれば、多少文章が長くなっても丁寧に書いた方が伝わりやすいこともあります。
このように、相手によってメッセージの送り方を変えるのは手間がかかることですが、うまく伝わらずに後々トラブルになる方が厄介ですので、最初に面倒なことがやれるかどうかがポイントになります。
そのようにしたい理由や背景も伝える
とくにクリエイターとのやりとりのときには、「やってほしいこと」だけでなく「そのようにしたい理由」も伝えることで、相手も動きやすくなります。
やってほしいことだけを伝えると、相手からすると自分が否定されている気になってしまうことが多々あり、
「自分のやり方が悪いのかな」「なんで自分の考えではダメなんだ」
とネガティブな感情になりがちです。
クリエイターは仕事柄、クライアントや上流領域からの指示が二転三転しがちで、相手を疑ってやりとりをしている人もとても多いため、あくまで「否定しているわけではない」ということは念入りに伝えましょう。
そこで、そのようにしたい背景や理由を明確に伝えることで、クリエイターはネガティブな感情にならずに、タスクの内容を受け入れて作業をしてくれやすくなります。
対等な関係という認識を持つ
Webディレクターはプロジェクトを統括する役割なのでチームメンバーの中で立場が一番上になりやすく、メンバーのみなさんもディレクターの立場の方が上だという認識になりやすいです。
チームメンバーがディレクターを上の立場だと認識する分には問題ありませんが、ディレクターがチームメンバーを下に見るような認識になってしまうと、どうしてもコミュニケーションが雑になりがちで、文章が伝わりにくくなります。
社内のメンバーとのやりとりで、明確に役職や立場に上下関係があれば良いですが、業務委託のメンバーで成り立っているチームの場合は、ディレクターもメンバーも対等の関係であるという認識を持ち相手をリスペクトして、丁寧なコミュニケーションを心がけましょう。
声を送るとニュアンスが伝わりやすい
テキストコミュニケーションの弊害は、文章だけでは言葉のニュアンスが伝わらないということ。
「お願いします」の一言とっても、受け手にとってはキツく感じてプレッシャーになってしまう人もいるでしょう。
ですが、これが声で「お願いします」と聞けば、言葉のトーンで相手がどのようなニュアンスで言っているのかが分かり、必要以上にプレッシャーを感じることもないはずです。
また、一度声を聞いたことがある人の文章は、その文章を読む時に脳内でその人の声で文章が再生されるため、テキストにより臨場感が生まれます。
声を送るといっても、日常的なメッセージをボイスメモで送るというわけではありません。
例えば、要所要所で動画を使った解説資料などを送ることで、相手に声を届けることができます。
- 記事制作マニュアルを動画で作成する
- 施策の方向性の資料を画面録画で解説する
- フィードバックを画面録画で解説する
など、プロジェクトを進める中でより理解してほしいところを動画解説することで、内容も伝わり、言葉のニュアンスも伝わるのでおすすめです。
人のメッセージをコピペで送らない
Webディレクターの立場ですと、上からの指示を全チームメンバーに伝えたいシーンなど、誰かに言われたことを別の人に伝えることも多いと思います。
その際に、言われたことをそのままコピペで相手に送ってしまうと、どうしてもニュアンスが伝わりません。
お互いに信頼関係で成り立っている間柄であれば、人からの文章をコピペで伝えても問題ありませんが、信頼関係が出来ていない間柄でしたら、必ず自分の言葉で相手に伝えるようにしましょう。
余計な含みはコミュニケーションを阻害する
人からのメッセージをコピペで送ってしまうと、「このメッセージの本意はなんだ?」と相手に余計な疑問を与えてしまい円滑なコミュニケーションを阻害してしまいます。
テキストコミュニケーションは、ただでさえ情報量が少なくて解釈が難しいので、余計な含みを与えずに、できるだけ自分の言葉で意図を伝えることが望ましいと思います。
丁寧なコミュニケーションが信頼関係を作る
以上がテキストコミュニケーションにおける注意点の解説でしたが、総じて言えることは「いかに丁寧にコミュニケーションが取れるか」が大切だということ。
文章で本意を伝えるのはとても難しく、手間がかかり面倒ですが、この手間を惜しまず丁寧にメッセージを送ることで、相手との信頼関係を構築することができ、日頃の業務もやりやすくなっていきます。
作業をしてくれるチームメンバーが居てこそプロジェクトを進めることができるので、Webディレクターとしては、チームメンバーが気持ちよく仕事できるようにするのも仕事の一環です。
いいチームを作るための「丁寧さ」も意識しながらマネジメントをしていただければと思います。