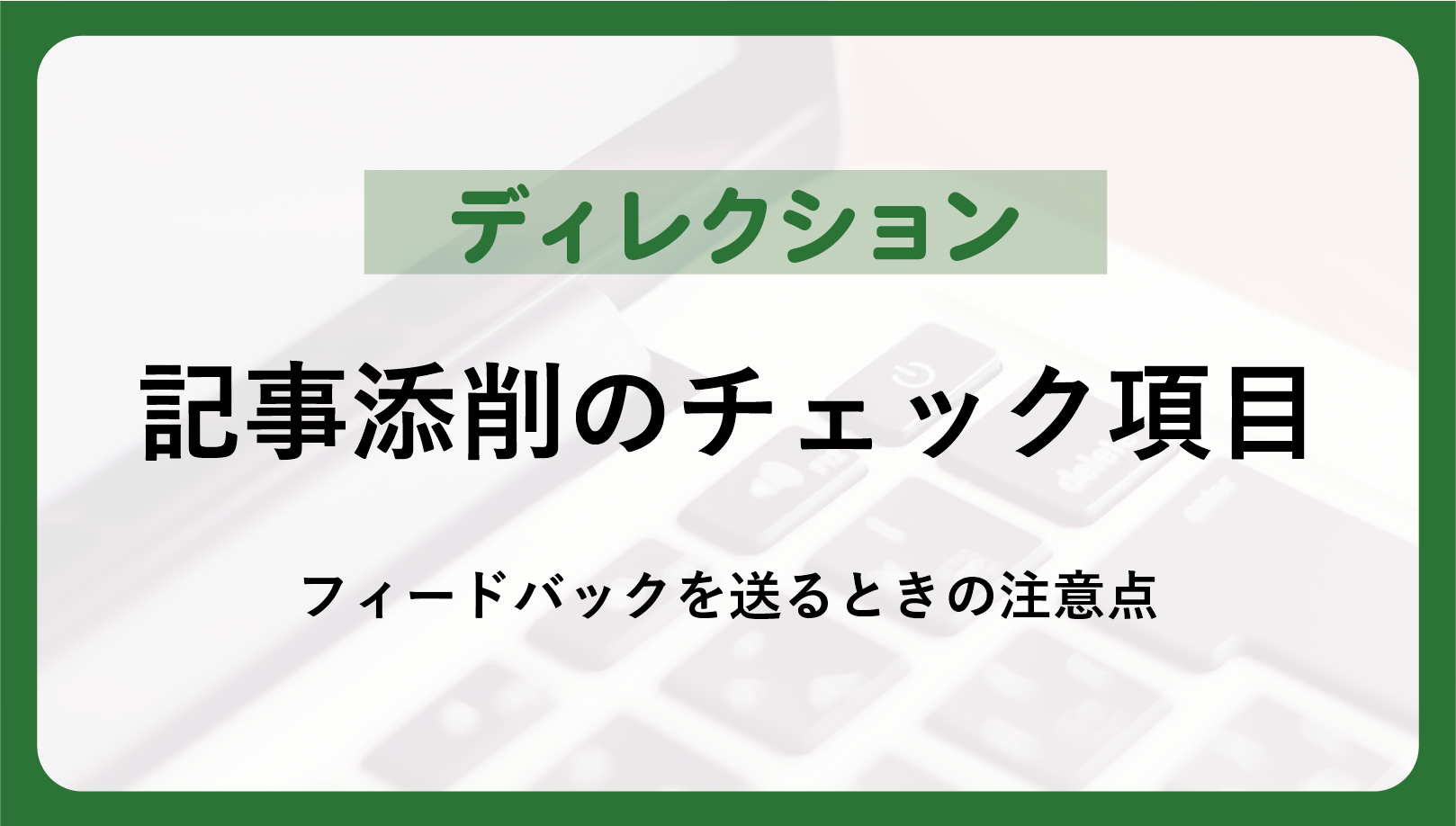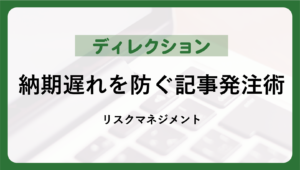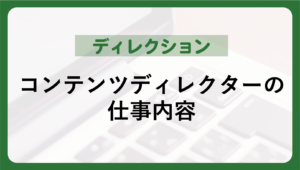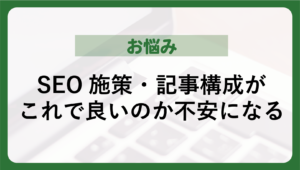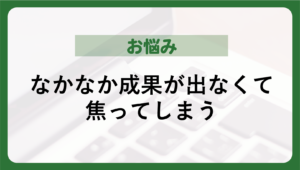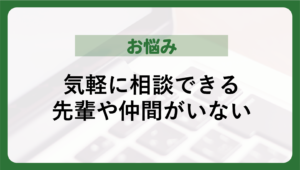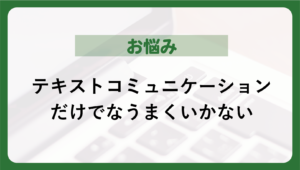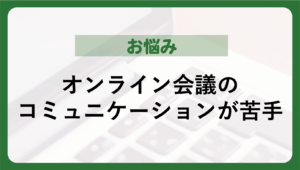今回は記事添削のやり方を解説します。
コンテンツディレクターは制作物のクオリティに対して責任を持つ仕事です。ユーザーと企業(メディア)の最初のタッチポイントになるのがこの記事コンテンツですので、メディアとして発信したいことが記事添削は業務の中でも重要な仕事になります。
【はじめに】フィードバックを送るときの注意点
それぞれのチェック項目に対して、どのようなフィードバックを送ればいいか合わせて解説しますが、そもそもライターに修正能力があるかどうかの見極めも重要になります。
修正能力とは文章を書き上げる力、つまり文章力が備わっていないライターにいくら修正依頼を送ってもまとめ上げることができません。
ライターとしては修正したつもりでも、初稿として提出された記事よりも読みにくくて破茶滅茶になって再提出されることもあるので、ライターの力量で対応できる範囲で修正依頼を送るようにしましょう。
もしライターが修正対応できないようでしたら、ひとまずその記事に関してはディレクターが修正をしてサイトに投稿するのが無難です。
また、自分がライターに求めるレベルが高い可能性もありますので、求めることは果たして報酬に対して適切か、その都度、振り返るようにしましょう。
記事をチェックするときの流れ
記事をチェックするときは、
- まず最初にざっと最後まで読んで
- 細かい箇所をチェックしていく
という流れで添削していきます。
全体に目を通さずに冒頭から入念に修正をしてしまうと、修正しているうちに落とし所が初稿とは全く別のところになってしまい、ゼロから書き直しをしなければ記事がまとまらない状態になってしまうので注意してください。
では、それぞれのチェック項目をみていきましょう。
記事添削をするときのチェック項目
これから解説するチェック項目は、あくまで一例です。添削のやり方に正解はなく、メディアやプロジェクトごとに大切にしていることがあると思いますので、必要な項目を参考にしていただければと思います。
ただ、現状で決まりやレギュレーションが無くて、添削の基準がわからないコンテンツディレクターの方は、1番から順番にチェックしていただくとスムーズに添削ができるようになっています。
①コピーコンテンツになっていないかチェックする
まずはじめに、原稿がコピーコンテンツになっていないかチェックします。これは目視ではなくツールを使ってチェックすることになります。
コピーコンテンツとは、他サイトのページをコピペで貼り付けてなんとなく形にした記事のことをいいますが、コピーコンテンツとする基準を設けて、依頼するライターには一律でその基準内でコピーチェックをします。
中には意図せず文章が一致してしまうケースもあるので、そのような場合はライターを咎めることなく、穏便に修正依頼を出しましょう。
段落全てコピーコンテンツになっているなど悪質の場合は、厳しく指摘をして、オリジナルの文章で書いてもらうように修正依頼を出しましょう。
また、コピーコンテンツを提出するライターはコンテンツ制作を仕事として行うにあたってのモラルがなく、ライターとして失格ですので、契約はその記事のみで終了するのが望ましいでしょう。
仮に大型契約をしてしまっているとしたら、契約書に基づいて契約解除の通達をします。
②メディアの意図や方向性と記事の内容がズレていないかチェックする
記事の全体をざっと読んで、メディアとして想定していた意図や方向性と、記事の内容がズレていないかチェックをします。
同じテーマで記事制作を依頼しても、書き手によってリサーチ方法が違ったり解釈が違ったりするため、内容自体は悪くないけれど、ディレクターが想定していた方向性とズレることは多々あります。
一つの段落だけなど部分的にズレているのであれば修正は難しくありませんが、記事の内容が想定とズレているときというのは、全体を通してズレていることが多いです。
全体を通してズレてしまっている場合は、部分的な修正では仕上げることができないので、書き直しとなってしまいます。
このような、記事の意図や方向性のズレが生じてしまうのは、前提の共有が不足しているときに起こりがちです。
特に、ライターに記事構成の作成から依頼している場合、前提が共有されていない状態ですと記事構成を作成する段階でズレが生じてしまうため、仕上がった記事は当然想定と違ったものになってしまいます。
記事構成からライターに依頼する際は、必ず構成ができた段階で一度ディレクターが目を通して、意図や方向性にズレがないか確認するようにしましょう。
フィードバックの注意点
全体的に想定していた意図とズレている記事を修正してもらう際は、どのようなことを書いて欲しいか、メディアとしての意図を共有して、記事構成をディレクターが作成してライターに依頼した方がズレることなく仕上がります。
ライター側からしたら、一度ひとつの原稿を仕上げているので、書き直しをするのは負担が大きくなってしまいます。前提の共有不足はディレクターの責任ですので、ライターの負担を軽減するためにも記事構成を渡したほうが親切かもしれません。
③文章に統一感があるかチェックする
記事の中で、文章の書き方や文体が変わっていないかどうかチェックをします。
例えば、
- 前半では「敬体(ですます調)」なのに後半では「常体(である調)」になっている
- 文章が急に上から目線になっている箇所がある
- 書き出しは柔らかいのに本文から言葉がきつくなる
など、記事の中でトンマナに一貫性がなくなってしまうと、読者の違和感になりページを離脱してしまいます。
また、文章に統一感がないと読者は「このサイトの内容は本当に大丈夫かな…?」と不審に感じてしまいます。
フィードバックの注意点
文章の書き方や文体については、基本的にはメディアとしてレギュレーションを定めてライターに依頼しますが、統一感のない文章の場合はレギュレーション通りに書いてもらうように修正依頼をします。
その際に、併せてメディアにある記事を参考として送ると文章のトーンや文体のイメージができて、ライターも修正がしやすくなります。
④記事の中で主張が一貫しているかチェックする
Webコンテンツの場合、基本的には「1記事・1メッセージ」として、記事の中では主張を一貫させます。
特に企業が運営するオウンドメディアの場合は、企業が主張するメッセージがあると思いますので、企業として統一して主張したいことがあれば、ライターに対してはその主張をもとに記事を作成してもらうように指示を出します。
そして、その主張が書かれているか、記事の中で主張にブレがないかをチェックしていきます。
主張があることで発信する側の立場が明確になり、メッセージ性が強くなるため読者に響くコンテンツになります。
逆に主張がない記事は内容が右往左往して読みにくいだけでなく、当たり障りのない内容になってしまい読者の印象に残らないコンテンツになってしまいます。
オウンドメディアを運営するということは、企業として伝えたいことや届けたいサービスを広めるためのWebマーケティングの一環として施策を実行していると思いますので、読者の印象に残らないコンテンツは施策の意味を果たしません。
記事を発注する際は、単なる受発注のやりくりだけにならないように注意をして、その記事がWebマーケティング施策としての意味があるコンテンツになるように、クオリティの維持に責任をもつのもディレクターの仕事なのです。
フィードバックの注意点
主張したいポイントがうまく伝わらないことがありますので、「どこで、どのような主張をするか」を明確にして修正依頼を送りましょう。
もし、主張したいことを追加するときに前後の文章との馴染みが悪いようでしたら、書き出し文に主張を書くと本文に影響なく盛り込むことができます。
書き出し文に主張を書くことでその記事内で言いたい結論が先に伝わるので、読者も読み進めやすくなります。
⑤結論が先に書かれいるかチェックする
結論というと、答えをそのまま書くものだと思われることも多いですが、答えだけが結論ではなく、主張を先に書いたり、この記事ではどのような内容が書かれているか書いたりすることも、結論と言えます。
つまり、「読者にとってこの記事を読み進めれば知りたいことが解決できるか」ということが先に書かれているかが重要です。
Webコンテンツは書籍などの紙媒体とは違い、すぐにページから離脱できてしまうという特性があります。
特に、TikTokやYouTubeショートなどを始めとするショート動画コンテンツが流行してから、ユーザーはネット記事を読み込むことをしなくなっている傾向にあります。
そのため、記事ページを見たときに冒頭の数行で読者が知りたい結論が書かれていないと、「このページは知りたいことが書かれていない」と思われてしまい、ページを離脱してしまいます。
たとえ、読み進めた先に結論が書かれていて、悩みが解決できる素晴らしい内容のコンテンツだとしても、読まれないことには意味を為しません。
チェックするときの注意点
記事をチェックするディレクターは、読みにくい文章だとしてもチェックするためにしっかりと読み込むので、読者も読むものだという感覚になりがちです。
あくまで仕事で読んでいることを忘れずに、読者視点ではどう見えるのかを意識してチェックするようにしましょう。
⑥情報に信憑性があるかチェックする
いまや、どの情報が正解でどの情報が間違ってるかがわからないほど情報溢れている時代なので、情報の信憑性の有無を判断するのは難しいところがあります。
特にネットに載っている情報だけをリサーチしてまとめる記事の場合は、リサーチした元サイトの情報に信憑性があるかどうかなど判断ができません。
情報の信憑性のチェックは、発信者としてのモラルや倫理観に関わるものなので正解がありませんが、読者に害が及ばないことや、本当に信頼してもらえるコンテンツを発信することの意識は忘れないようにしましょう。
その上で、ライターの原稿に気になる箇所があるようでしたら、情報の出所や参考にしたサイトを提示してもらい、その情報に問題がないかどうかを判断します。
フィードバックの注意点
そのときに「誰が発信している情報か」を基準とすると判断がしやすくなります。「何を言っているのか」ではなく「誰が言っているのか」です。
Web上の情報の信憑性についてはGoogleも「誰が言っているか」を重要視しており、その基準としてE-E-A-Tという概念を設けています。
自分たちがそのジャンルにおいて専門性のある企業でしたら発信する情報に迷いはないと思いますが、外部ディレクターとしてクライアントのコンテンツディレクションをしている場合は、何を持って信憑性があるとするかはディレクターの判断になります。クライアントと密に擦り合わせをして、読者が信頼できるコンテンツを制作するようにしましょう。
⑦対策しているキーワードが含まれているかチェックする
これはSEO対策としてコンテンツ制作をしている場合のチェック項目ですが、SEO記事の場合は上位表示させたいキーワードに対して、そのキーワードで上位表示をするためのコンテンツを作成します。
そのため、記事内に対策キーワードが含まれているか、あるいは、不自然に含みすぎていないかチェックをします。
特に、
- タイトル
- 各見出し(主にh2タグ)
に対策キーワードが含まれていることによって、Googleの検索エンジンは「そのキーワードについて書かれているページだ」と判断します。
いくら内容が素晴らしくても、対策したいキーワードが記事内に含まれていなければ検索上位表示はされませんので注意してチェックをしましょう。
SEO対策については非常に専門的な施策の一つであり、ここで全てを解説できるほど簡単ではありませんが、コンテンツディレクターとしては、記事のタイトルと見出しに対策キーワードが含まれているかチェックして、対策キーワードに対して記事が書かれているかどうかの判断をできるようにしましょう。
⑧誤字脱字がないかチェックする
誤字脱字は校正ツールなので簡単にできますが、念の為目視でもチェックしましょう。
誤字脱字の修正については、目に余るほどではない場合は修正箇所を指摘して差し戻しのやりとりをする方が手間になってしまうことがあるので、ディレクター側で修正をしてしまい、修正した箇所と以降の記事で誤字脱字がないように留意していただくことを伝えるだけで問題ないと思います。
もし、ひとつの記事内で誤字脱字が少なかったとしても、それが何回も続くようでしたら、ライターに誤字脱字のチェックを入念にしていただくように通達しましょう。
⑨冗長表現になっていないかチェックする
冗長表現(じょうちょうひょうげん)とは、回りくどい言い回しや、間延びした言い回しで文章を書いていることをいいます。
冗長表現になることで、何を言っているのか伝わりにくい文章になり、読者に伝えたいことが的確に伝わらないので、キレ良く言い切るような文章になっているかチェックをします。
ライターが冗長表現になってしまう原因の多くの場合は文字数を稼ぐためです。少しでも文字数を稼いで報酬をアップさせたいときや、指定の文字数に足りないときに、あえて回りくどく文章を書く傾向にあります。
フィードバックの注意点
冗長表現はしっかりと指摘をしてキレの良い文章を書いてもらうように修正してもらい、その結果文字数が足りない場合は、別の話題を追記してもらったり、具体例を記載して文章に深みを持たせたりしながら文字を調整します。
⑩文章にリズムがあるか、単調になっていないかチェックする
文章が段落になっておらず一文が並んでいるだけの記事は、文章が単調になってリズムが悪いので読み手にストレスを与えてしまいます。
例えば、語尾が「〜ます」が続いていたら、前後の一文をまとめて段落にするように修正したり、接続詞の「また」が連続して使われているようでしたら別の接続詞に変えたり、新たに小見出しを追加してリズムが生まれるように修正をします。
リズムがあって読みやすい文章を執筆できるかどうかはライターの能力次第ですが、ディレクターも記事をチェックするにあたり、どのようにすればリズムを作れて単調にならないか、修正のフィードバックを送れるくらいまでの文章力があった方が望ましいでしょう。
綺麗で読みやすい文章は、Webコンテンツよりも編集者がしっかりとしている書籍の方が参考になります。勉強も兼ねてWebマーケティグ関連の書籍を読むと、自分の文章力も高まっていくのでおすすめです。
⑪ユーザーに自分ごとと思ってもらえるような事例があるかチェックする
読者に響くコンテンツの条件の一つに、自分ごとと思ってもらえる文章かどうか、というものがあります。
読者は「自分のことを書いてある内容だ」と思って初めて商品を購入したり、会員登録をしたり、次のアクションを起こします。
企業が運営しているオウンドメディアは集客のために運営していると思いますので、一つひとつの記事で読者に次のアクションを起こしてもらえるような内容にすることが求められるでしょう。
読者に自分ごとと思ってもらうためには、具体例などを用いてユーザーが自分ごととしてイメージできるような描写が必要です。
読者が記事を読んで行動を起こそうと思える文章を書くのは高度な技術が求められるので、クラウドソーシングなどで広く募集したライターにそこまで求めるのは厳しいかもしれません。
フィードバックの注意点
記事をチェックして、文章に具体例や例え話などの描写がない場合は、「この箇所に〇〇のような具体例を追記してほしい」とピンポイントで追記を依頼してライターのスキルを補いましょう。
また、具体例を記載するためには自分がその経験をしていなければわかりやすく書けないと思いますので、そこまでをライターに求めずにディレクターが追記する形でも良いと思います。
⑫メディア内の他の記事と関連性があるかチェックする
複数のライターに依頼しているメディアの場合は、どうしても別のライターが書いた記事のことは頭に入っていないのでその記事単体での仕上がりになってしまいますが、メディアとしては他の記事同士に関連性を持たせて主張に一貫性がなければなりません。
一つの記事内で一貫した主張になっていることや内容に整合性を持たせることは最低限必要ですが、メディア全体のことを考えて内容チェックができるようなレベルの高いディレクターを目指しましょう。
そのためには、ビジネスにおいてのメディアの目的を理解して、マーケティングとしてのメディアの役割を把握することが必要で、マーケティングの全体像を把握する力が求められます。より高度なディレクションスキルですが、マーケティング思考を兼ね備えたディレクターの価値は高く求める企業も多くなります。
記事の添削もディレクション力を高める場にしよう!
オウンドメディアにおける記事というのは、ユーザーがその企業やサービスのことを知るためのきっかけとなる最初のタッチポイントになるため、実は非常に重要な役割を担っています。
記事添削やライターへのフィードバックは地味で根気のいる作業でなかなか日の目を浴びないポジションですが、その重要性を理解して責任感を持って記事添削を行えば、マーケティング思考も養われていきディレクターとしての経験値もどんどん高まっていきます。
チェック項目が多いので実務の場では大変かもしれませんが、記事添削で迷ったときにこの記事を振り返って参考にしていただければと思います。
今回紹介したチェック項目の一覧表をPDFで用意しましたので、ご自由にお使いください。