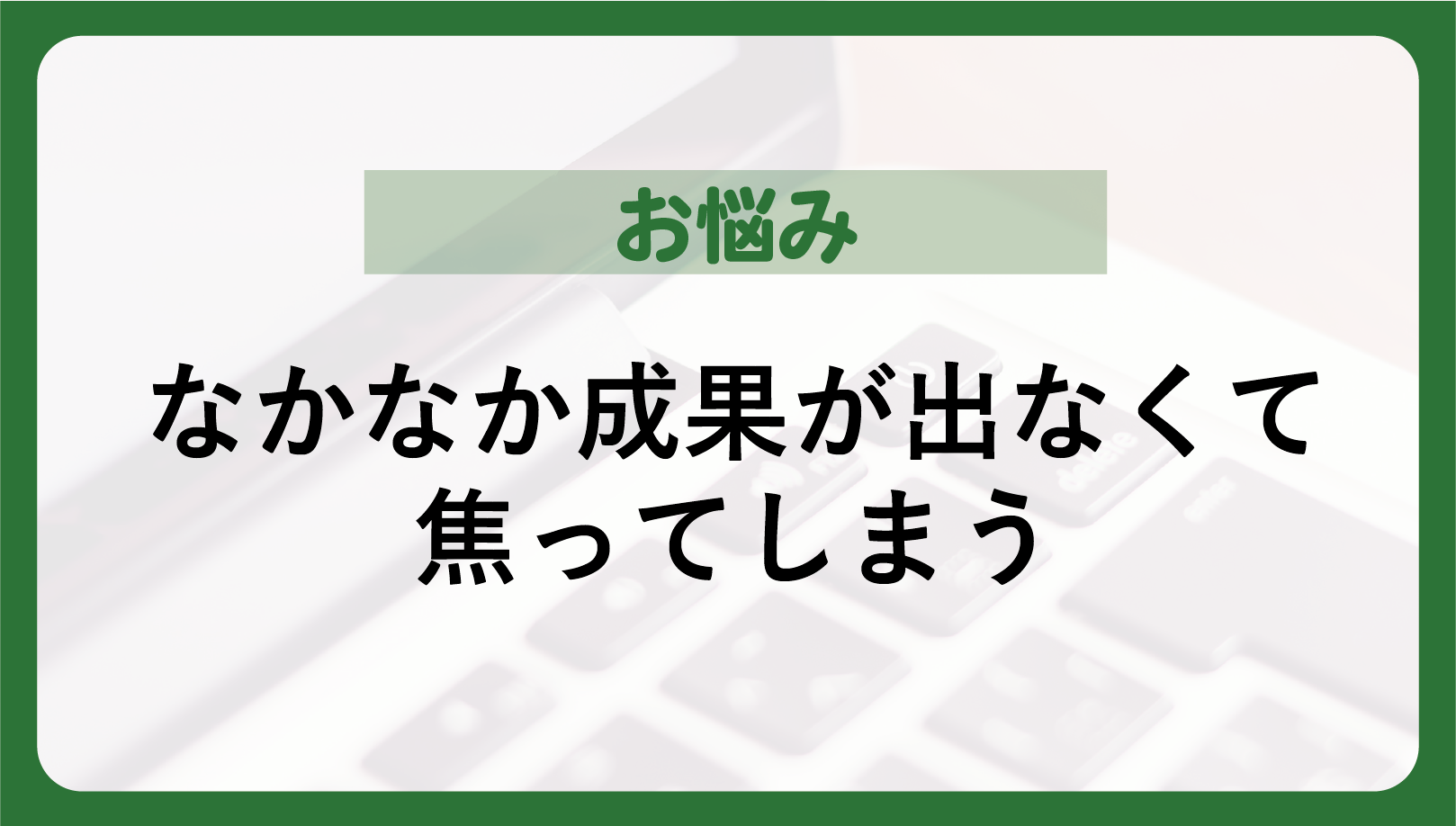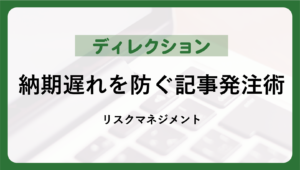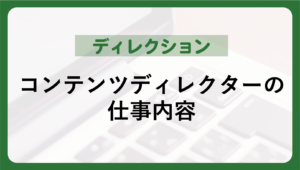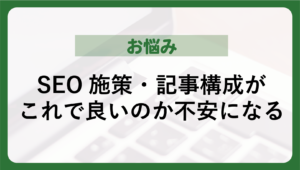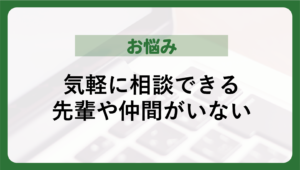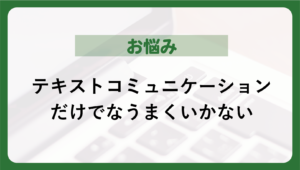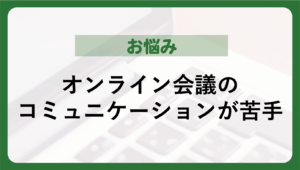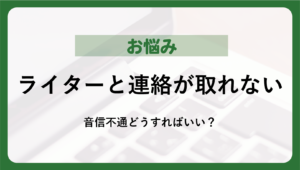自分がディレクターとして携わっているプロジェクトがなかなか成果が出ないとき、プロジェクトマネジメントをしている立場として「なんとかしなければ」と焦ることもあるでしょう。
特にウェブマスターの社内ディレクターの場合は、そのプロジェクトの位置付けも把握できてしまうために、責任を強く感じてしまうかもしれません。
では、なかなか成果が出ないときの「成果」とは一体何を指すのでしょうか?
ここを明確にして問題点を鮮明にすることで、必要以上に背負うこともなくなりますし、冷静に状況を判断して対応することができます。
オウンドメディアの構築、コンテンツマーケティングにおいては、
- ユニークユーザー数
- ページビュー数
- 検索順位(SEO)
- 資料DL数
- メルマガ登録数
などが代表的なKPIとして設定されますが、そもそもKPIが設定されていないと成果が出ている、出ていないの判断ができません。
また、これらのKPIが現実的かどうかによっては、必ずしもコンテンツディレクターだけの責任ではなく、目標設定をした上流層の責任の方が大きいかもしれません。
今回の記事では、Webマーケティングのコンテンツ戦略において「成果が出ないときに確認すべきチェックリスト」をご紹介しますが、先にリスト一覧をお伝えすると
このような項目になります。
項目を見ただけでも冷静に見直すべきところが思い当たる方もいるかもしれません。
ではそれぞれのチェックリストの項目について、詳しく解説していきましょう。
成果が出ないときに確認すべきチェックリスト
成果を測る目標を設定しているか
冒頭でも軽く触れましたが、目標を設定していなければ成果を測ることはできません。
これは、なんとなくオウンドメディアの構築を始めてしまった企業にありがちですが、
- なんとなく良さそうだから
- SEOが集客に良いらしい
- 他社がやっているからウチもやりたい
などの理由で始めたまま、その先、自社に適した目標が設定されないことが多々あります。
そのため、客観的に見れば「ここまでの数字が出ていれば上出来ですよ」というケースもあり、悩みや焦りが一気に解消されることも。
まずは現状分析から始めよう
オウンドメディアの目標が明確に設定されていない場合は、まずは現状分析から始めます。
以下の項目を1ヶ月あたりの数値を出してまとめてみましょう。
- ユニークユーザー数
- ページビュー数
- 検索順位(SEO)
- 資料DL数
- メルマガ登録数
これらのデータを出したことがないとしたら、出てきたデータを見るだけで何か気づくことやひらめきがあるかもしれません。
もし自分では数値の良し悪しが判断できない場合は、一度専門家に確認してもらいましょう。
ランサーズ、ココナラなどのクラウドソーシングのプラットフォームで「サイト分析します」というサービスを販売している方がいるので、そのような方に分析を依頼すればコストは最小限で現状を把握することができます。
それを受けて、
- 本来期待していた成果との差分
- 目指していく目標値
などを、まずは仮説で構わないのでディレクターが叩き台として目標値を設定します。
その上で、その数値を元に上流層と相談して、オウンドメディアのKPIを明確に設定しましょう。
成果を判断するには期間が短すぎないか
Webマーケティングである程度成果が出るまでには時間がかかります。Web経由で最初のお問い合わせが来るまでに半年〜1年かかることも少なくありません。
また、Web集客で売上に影響を与えるぐらいまで成果を出すには数年かかることもあります。
特に、これまでにWebマーケティングを本格的に取り組んでいなく初めて取り組む場合は、社内にノウハウも溜まっていないと思われるので、短期間で成果が出るのはまずありえないと思っていただいた方が良いでしょう。
あなたがWebマーケティングに取り組んでいる期間はどのぐらいでしょうか?
もし、取り組んでからまだ2〜3ヶ月ぐらいしか経っていないようでしたら、成果の判断をするのはまだ早すぎます。2〜3ヶ月程で社長や上司から成果を問われるようでしたら、社内でのWebマーケティングに対する認識が間違っている可能性があるので、今一度、Webマーケティングに取り組む姿勢や方針を見直した方が良いかもしれません。
何年も成果が出ていない場合は?
仮に、Webマーケティングに取り組んでから2年以上経っても、いまだにこれといった成果が出ていないようでしたら、それはWebマーケティングの施策の方向性が間違っている可能性があります。
- そもそも成果が出ないやり方でやってしまっている
- お客様が求めていないことをやってしまっている
- 競合が強すぎて太刀打ちできない
などのパターンに陥っていることが考えられますので、「このやり方は本当にあっているのか?」をじっくりと見直して、必要に応じて専門家に意見を仰ぐようにしましょう。
成果が出るまでは少しの変化も見逃さないように
Webマーケティングは成果が出るまでは我慢の繰り返しです。ディレクターとして時に風当たりが強くなることもあると思いますが、成果が出ればみなさんにわかってもらえるようになります。それまではなんとか耐えて、淡々と日常の業務をこなしていきましょう。
また、成果が出るまでの間にもWebサイトではさまざまな変化が起きています。少しずつアクセス数が増えてきたり、検索順位が少しずつ上がってきたり、検索からの流入が増えてきたり。
そんな小さな変化も見逃さないように常にGoogleアナリティクスなどの分析ツールはチェックするようにしましょう。
そして、小さな変化があったときは、そのデータをレポートにして周囲の人や上司、クライアントに報告するようにしましょう。少しでも成長していることを感じられると周りの反応も変わってきます。
施策に対して適切な成果はどのくらいか
Webマーケティングで成果を出すために様々な施策を実行していると思います。オウンドメディアでコンテンツマーケティングを実施する場合は、主な施策内容としては記事制作になると思います。
その施策内容と実施数に対して、どのぐらいの成果が妥当なのか、その適切な数値を把握しておくと良いでしょう。
あなたが「思うような成果がでない」と悩んでいるとき、そのときの施策内容では成果が出なくて当然かもしれません。
例えば、運用歴が3ヶ月で現在サイトに20記事しか投稿されていない場合、そのサイトから月間100件のお問い合わせを獲得することは残念ながら現実的ではありません。
運用歴と投稿記事数を考慮したときに、現在想定している成果は妥当な数字か、また想定している成果を出すためにはどのぐらいの記事投稿数が必要なのか、冷静に判断をしてみてください。
競合サイトと単純比較は難しい
競合サイトをみて「この会社のようにメディアを作りたい」というパターンでコンテンツマーケティングを実施する企業は多いですが、そのときに競合サイトが投稿している記事数をチェックして「少なくともこのサイトと同じぐらいの記事数を投稿しよう」と目標を立てることがあります。
しかし、記事数を同じくらい投稿したところで、同じくらいの成果が出ることはまずありません。Wコンテンツマーケティングで成果を出すためには、記事数だけでなく様々な指標の上にその結果としてメディアが成り立っています。
もし記事数を比較の指標として重視しているようでしたら、施策に対しての適切な成果を見誤る可能性があるので、競合サイトがやっている施策を多角的に分析するようにしましょう。
企画の段階で想定が甘くないか
これはWebディレクターの責任領域ではなく、Webプロデューサーや役員、経営者などのいわゆる上流領域での責任になるのですが、企画の段階で成果に対する想定が甘くなかなか思うような成果が得られないケースです。
※Webディレクターもプロジェクトの重要メンバーとして企画に参加しているようでしたら、ディレクターにも責任が及びます。
企画をするのはディレクターよりも上流領域で行われることが多いですが、Webマーケティングに疎い経営者や役員の場合は、なんとなくのWebの認識から「このぐらいはいけるんじゃない?」と甘く見積もりがちなところがあります。
その甘い想定で企画をしてしまうため、ディレクターのところに仕事が回ってきた段階ではすでに成果が出ない企画として進めなければならず、ディレクターの力量では何ともならないこともあります。
このような企画ではなかなか成果を出すのは難しいので、深く悩む必要はありません。
「この企画では成果が出ない」と言える勇気を持とう
ディレクターは時に上司やクライアントに対して厳しく意見をいう場面も必要です。ディレクターは現場監督としてWebマーケティング現場の肌感覚が染み付いており、経験を重ねていくうちに企画をもらった段階で「これは想定が甘いぞ…」「この企画で成果を出すのは難しいんじゃないか?」というように、肌感覚で成果が出るかどうかを判断できるようになります。
しかし、上流領域では現場感を持ち合わせておらず、成果が出る出ないの想定ができずに空想で企画を進めてしまうことがありがちです。
ですので、現場の意見としてディレクターからはっきりと「この企画では成果が出ない」と伝えることも重要なのです。
また、肌感覚で成果が出ないと感じている中でプロジェクトを進めてしまうのはお金だけでなく時間や人材など様々なリソースを無駄にしてしまうことになります。プロジェクトを進めている中で「やっぱりこの企画では成果が出ないんじゃないか?」と違和感を生じたときは、勇気を持って伝えるようにしましょう。
意見をいうときは代替案を持っていく
「この企画は成果が出ない」と言われると、言われた側の上司やクライアントは気を悪くしてしまうかもしれません。今後の関係もあるので穏便に物事を進めたいはずですので、意見をいうときには必ず代替案を持っていくようにしましょう。
頭ごなしに否定をするのではなく、これまでの企画を踏まえて、より良くするためにはどうすればいいか。という視点で意見を持っていくことで、相手も受け入れやすくなります。
時にディレクターはプレゼン能力も求められるのです。
パートナー会社は適切な施策をしてくれているか
Webマスターとしての社内ディレクターの場合、Webマーケティングの戦略を考えてくれるパートナー会社と一緒に施策を行っていることもありますが、そのパートバー会社に適切な施策を提案してもらっていない場合、なかなか成果に繋がらないことがあります。
パートナー会社は、
- Webサイト制作会社
- Webマーケティング会社
- SEOコンサルティング会社
などがあり、それぞれ得意不得意があるので自分の得意領域を超えた施策については、適切な提案ができない場合があります。
悪質な場合は、もともと成果が出ないことがわかっているにもかかわらず、仕事が欲しいがために無理やり営業をかけてくるパートナー会社です。
また、パートナー会社が経営層と付き合いがあるからという理由や、長くWeb周りの面倒を見てくれているからという理由で付き合いを続けている場合も注意が必要です。
もし、あなたがパートナー会社が提案する施策に違和感があるようでしたら、その違和感はほとんどの確率で正しいと思われるので、パートナーに別の施策を提案してもらうように打診したり、場合によってはパートナー会社を変更したりしながら、成果が出る方向にシフトしていきましょう。
制作したコンテンツは本当にSEO対策になるか
オウンドメディアでコンテンツマーケティングを行う際の基本的な手法としては、記事を使ってSEO対策を行ういわゆるコンテンツSEOを行うと思います。
そのコンテンツSEOのために制作したコンテンツが全くSEO対策になっていないこともあるので注意が必要です。
SEOというのは一律で行える対策はなく、同じコンテンツSEOをやるにしてもそれぞれのサイトによって制作すべきコンテンツの内容や、対策すべきキーワードが異なります。
そのため、制作したコンテンツがそのサイトに適切に作られていない場合、いくらSEO対策のために記事を量産したところで成果が出ることはありません。
SEO対策は一朝一夕にいかないためコンテンツをいくら投稿しても成果が出ない期間は数ヶ月続きます。その期間を考慮しても成果が出ない場合は、コンテンツの制作方法に問題があると仮説を立てることができます。
コンテンツ制作会社は本当にSEOができるか見極めよう
SEOコンサルティング会社は「良い記事を書いて投稿しましょう」「投稿した記事は資産になります」などそれらしいことを言いますが、漠然とした大枠の話しかできない会社は危険です。
毎月発注している記事が全く成果を出さずに無駄に終わってしまうこともあるので、制作したコンテンツがしっかりとSEO対策として効果があるのか一度精査して、このまま継続すれば本当に成果が出るのか見極めましょう。
もし、このまま継続しても成果が出ないと判断した場合、同じ会社に改善を求めても成果が出るコンテンツは納品されません。そもそもSEO対策になるコンテンツを作成できる能力を持っていない会社ですので、いくら突いてもお金と時間の無駄になってしまいます。
パートナー会社を切り替える際は、何社か見積もりをとって一番相性が合いそうな会社を選ぶようにしましょう。
「焦り」や「違和感」が生じたら冷静に現状を分析する
ディレクターとして「焦り」や「違和感」を感じることはとても素晴らしいことです。危機管理能力を持つことでプロジェクトが大きくブレることなく前身することができるので、焦りを感じるぐらいの責任感と危機管理能力がちょうど良いと思います。
ディレクターの能力が原因で結果が出ないようでしたら、勉強をしてそれを実践でやってみることを繰り返しながら、少しずつ自分も成長していきプロジェクトの成果にも跳ね返せるようにしていきます。
ただ、今回のページでも多く触れたように、Webマーケティングの成果については必ずしもWebディレクターだけの責任ではないことが多く、プロジェクトマネジメントを卒なくこなしたとしても、それが成果に繋がらないことも。
それは本記事の中でも触れたように、そもそもの企画の段階で方向性がズレていたり、上流領域の認識がズレていたり、パートナー会社の能力がなかったりすると、ディレクターの能力だけではどうにもなりません。
もしあなたがそのような状況にいるのであれば、必要以上に責任を負わず、現状を打開する方向にエネルギーを注ぐようにしましょう。
成果が出ないときの原因と解決策については本記事でたくさんのヒントと共に記載しているので、ぜひ何回も読み直していただければと思います。