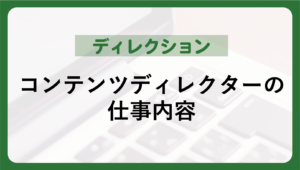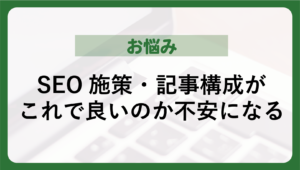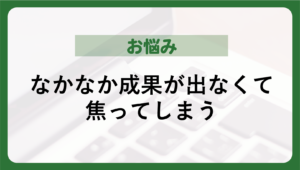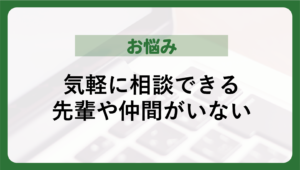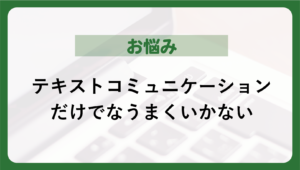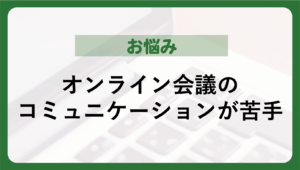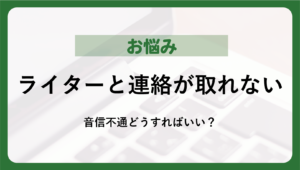いい仕事をする上でスキルよりも重要といっても過言ではないのが「信頼」ですが、タイトルにあるような納品遅れや本数不足などのミスは信頼を損ない、売上が減ってしまうだけでなく自分の仕事を圧迫し疲弊してしまいます。
コンテンツディレクターとしては、クライアントと信頼関係が成り立った上で仕事ができると、想定すべきシナリオが最小限に抑えられるので、余計な気遣いや根回しをしなくて済み、仕事がとてもやりやすく、精神衛生的にも健全な状態でいられます。
クライアントから記事制作の依頼があったとき、特に新規の依頼であればクライアントとの信頼関係はゼロの状態からスタート。コンテンツディレクターとしては記事を納品することだけでなく、信頼関係の構築にも意識を向けることも仕事の一つだと心得ておきましょう。
さて、記事制作においてありがちなトラブルが「納品遅れ」。納品遅れはクライアントからしたらディレクターの仕事に対して不信感を募らせるだけでなく、納期遅れを野放しにしているとして会社としての信頼度にも影響しかねません。
また、納品が遅れてしまうと、単に納品が遅れたという認識だけでなく、
「どこか適当に書いている箇所があるのでは?」
「やっつけで文字数を埋めただけなのでは?」
などと納期以外の品質の箇所にも不信感を抱かれてしまいます。
得てして、このような自体はコンテンツディレクター自身のミスというよりも
「ライターが納期に間に合わなかった」
「ライターが予定記事数を書けなかった」
「ライターが飛んだ」
など、ライター側に問題があることが非常に多いですが、クライアントにとってはライターの事情など知る由もなく、言い訳にできることでもありません。
ライターのトラブルを言い訳にするのはディレクターとしての力量不足を示しているようなもので、それもまた不信感を募らせる要因になります。
ディレクターとしては悔しいことでもあり頭を抱えますが、できることは、納期遅れを未然に防ぐためのリスクマネジメントしかありません。
今回の記事では、納期を確実に守るためにどのように記事発注をしてリスクマネジメントするのか解説していきます。
記事制作におけるリスクマネジメントとは
ライターを信じすぎるのは危険
まず初めに
ライターは納期を守らないし品質も悪い
という前提でライターを募集することがポイント。そして、真面目に対応してくれるライターは全体の2割程度しかいないというつもりで記事を発注しましょう。
これは決してライターを見下してみているわけではなく、そのような心持ちで慎重にライターを採用することが大切という比喩表現です。
実際に納期を守らず対応に困ってしまうライターがいる以上は、ネガティブなシナリオも想定してライターを選定しましょう。
あなたがライターからコンテンツディレクターに転身したのであれば、おそらくライターとして優秀だったので転身できたのだと思いますので、「納期を守り高品質な記事を納品する」ことは当たり前に行っていたと思います。
しかし、世の中のライターの8割は、優秀なライターにとっては当たり前のことができないのが実情なのです。
また、優秀なライターだった方が陥りやすいのは、
「こんな私もできたんだから、みんなできて当たり前」
と思ってしまい、知らずのうちに高い基準で記事発注を行っていること。
ライターを信じて記事を発注したいですし、クライアントとディレクターの間の信頼関係が大事ならば、当然ながらディレクターとライターの間の信頼関係も大事なので、ライターを信じて依頼したいですが、心を鬼にして「疑う」こともときには必要なのです。
まず第一にこのようなマインドセットでディレクションを行うことを意識しましょう。
記事制作費の中に「リスクヘッジ」のコストを含んでいるか
次にコストの話ですが、クライアントから頂く記事制作費の内訳に「リスクヘッジ」の予算を含んでいるでしょうか?
記事制作においてのリスクやトラブルは
リスク:ライターが納期に間に合わない、品質が悪い状態で納品される
トラブル:納品遅れによるデスマーチの発生
などが考えられ、これらの対応には当然コストがかかります。
ライターは修正対応をするのもコストがかかりますし、ディレクターにデスマーチが生じた場合は、当然残業代などのコストがかかります。
フリーランスとして働いている場合は、追加の修正費や残業代を貰えない可能性も高いので、その場合は時間的損失が大きくなり、お金に換算すると負担は大きいですよね。
トラブルが起きてからそれに対応する予算を捻出するのは至難の技で、クライアントから追加で費用を頂くことはできないと思ってください。となると、その費用を負担するのは自社(ディレクター)側になりその分は赤字です。
会社の赤字を避けることはもちろん、ディレクター自身やチームメンバーの損失を避けつつ、クライアントに余計な負担をかけさせないためにも、制作費の内訳にあらかじめリスクヘッジの予算を含めるようにしましょう。
「トラブルは起きる」ことを前提とするならば、それも想定して予算を管理するのもディレクターの仕事なのです。
リスクヘッジに生じるコストとは?
ここからは、実際にどのようにリスクヘッジを行うか、実例を想定しながら解説します。
ケース①:「納品遅れ」に備える
ケース②:「ライターと連絡が取れなくなった」に備える
ケース③:「SEOの効果がない」に備える
ケース④:「クライアントからの追加要望」に備える