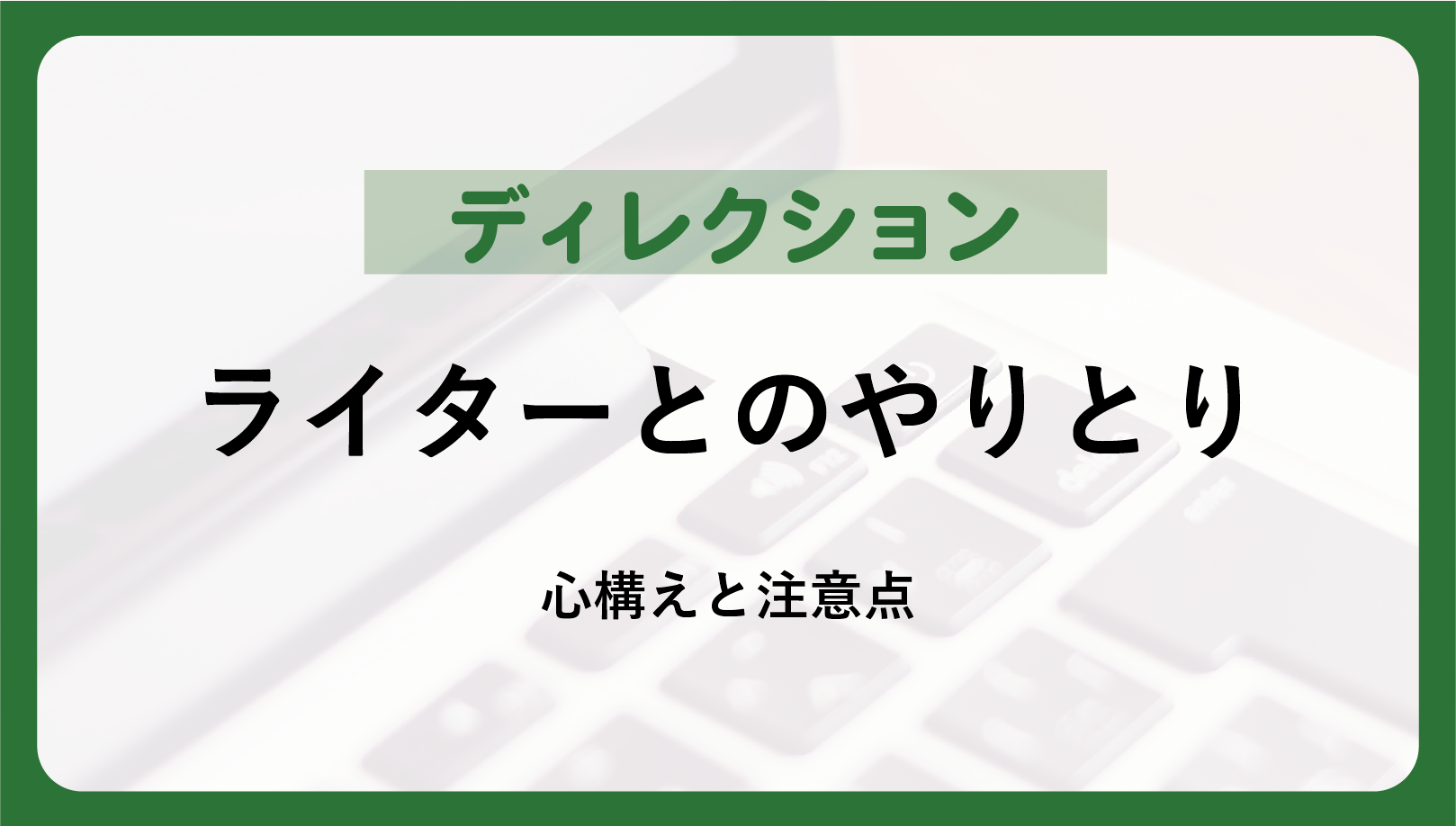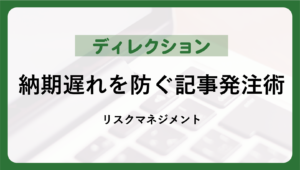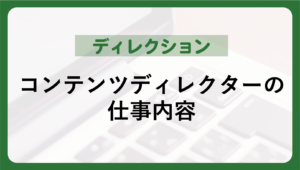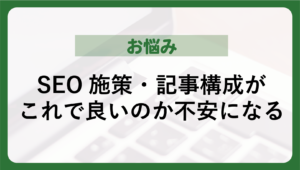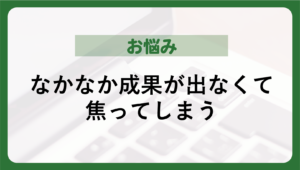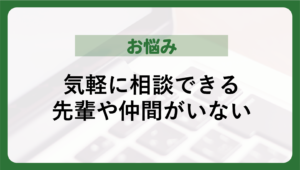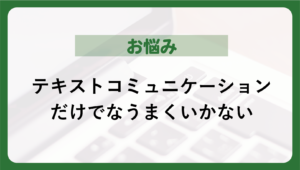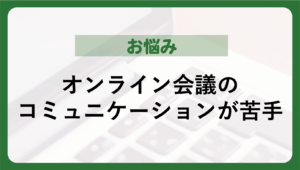ライターを採用したらいよいよコンテンツ制作チームとして本格的に始動します。ディレクターにとっては、ここから制作物をまとめてサイトに投稿するまでや、クライアントに納品するまでは業務が忙しくなっていきます。
できるだけ工数を削減して円滑にプロジェクトを進めていきたいところですが、どうしてもライターとの間にトラブルが発生しがちで、その対応に追われててんやわんやしてしまうこともあるでしょう。
ライターからの納品が遅れたり、求める品質で納品されなかったりすることもあると思います。
ですが、ディレクターとして大事なマインドセットを先にお伝えしますが、ライターの不手際やミスは全てディレクターの落ち度だと思うようにしましょう。
「ちゃんと仕事をしないライターが悪いんじゃないか」と思うかもしれませんが、ほとんどの場合はディレクションによってライターとのトラブルは防げます。
ということで今回は、問題なくプロジェクトを進めるためにディレクターが意識することとして、ライターとやりとりするときの心構えと注意点を解説していきます。
なぜライターとの間にトラブルが起きてしまうのか?
多くのライターと取引をしていると、どうしてもトラブルが発生しがちなもの。納品が遅れることや、求めていた品質で納品されないなんてことは、残念ながら少なくありません。
それだけでなく、急にライターと連絡が取れなくなることや、お金を振り込んだ後に急に品質が落ちる、というトラブルも稀ではありません。
一方で、ディレクターの不注意でライターが気を悪くしてしまうこともありますし、悪気はなくてもライターの労力を金額以上に使わせてしまった、ということもあると思います。
このように、ライターとの間にトラブルが起きてしまう要因は、ほとんどの場合は「コミュニケーション不足」によるものです。
ここでいうコミュニケーションとは、ディレクターとライターで直接メッセージのやりとりをしているときだけでなく、ディレクターとライターの接点になりうるもの全てを指します。
例えば、
- 募集要項
- 募集文
- 提案文
- 記事執筆マニュアル
- レギュレーション内容
- 記事構成
- 納品物
- フィードバック内容
などですが、つまりライターを募集したときから納品完了するまでの全てにおいて、何かが不足していたり落ち度があるためにトラブルが発生します。
そして、このようなトラブルは基本的にディレクターの力量でいくらでも減らすことができますし、マネジメント力で円滑に進み結果を出せるコンテンツ制作チームを構築することもできます。
次の章では、円滑にプロジェクトを進めるために、ディレクターが気をつけることや注意点をご紹介します。
もし、ライターから求める品質の記事が納品されなかったり、いつも何らかのトラブルに巻き込まれてしまうというディレクターがいるようでしたら、ライターを募集したときの募集要項にさかのぼって「なにが悪かったのか」を探してみましょう。
ライターとやりとりするときに気をつけることと注意点◯選
仕事内容に見合った単価になっているか確認する
まず初めに、仕事として記事制作を発注する以上は、その仕事内容に見合った単価で依頼するようにしましょう。
当たり前のように思うかもしれませんが、SNSを見ていると「その単価で受けてライターさん大丈夫なの?」と思わず心配になってしまうような単価で受注しているライターさんもいます。
価値には適正な対価をお支払いするのがマナーですので、仕事内容に見合った単価で発注しているか確認しましょう。
中には悪気があって見合わない単価で発注してしまっているディレクターもいるかもしれませんが、記事を発注するときには何となくで構いませんので相場感を調べてから発注するようにしましょう。
もし、相場よりもかなり低単価だと認識して発注しているのであれば、やはり相応の品質でしか納品されなかったり、ビジネスマンとしてのマナーに欠けるライターが集まる可能性が高いです。当然ディレクションも必要以上に工数が増えていくばかりで、単価は安くてもコスパは悪いと言わざるを得ません。
入口(募集要項)で間違うと出口(納品)までチグハグは拭えませんので、入口からしっかり整えてライターを募集するようにしましょう。
レギュレーションを用意して執筆前に確認してもらう
依頼するライターが決まって正式に採用をしたら、執筆作業に入る前に記事執筆に関するレギュレーションを確認してもらい、メッセージで了承の確認をとってから作業を開始してもらうようにしましょう。
レギュレーションとは「決まりごと/規定」のことをいい、記事制作に当たってのマニュアルに執筆に際しての決まり事を記載することもあると思います。
レギュレーションは記事執筆に際しての基本的な決まり事をまとめたもので、ここでしっかりと決まり事を定めることで、作業開始してからのライターからの質問を最小限に抑えることができます。
また、レギュレーションがしっかりしていることで、ライターも安心して執筆作業を開始できますし、無駄なミスも最小限に減らせます。
ディレクターがライターとやりとりするときに、1名〜2名のライターであれば質問などにも都度対応ができますが、抱えるライターが増えてくると、同じ質問に答えるのも大変になってきますし、同じ注意をするのも煩わしくなります。
ライターからの質問はまとめて書き残しておこう
レギュレーションが決まっていなかったり、マニュアルを用意できていないようでしたら、まずはライターからの質問や要望をエクセルなどに書き残しておきましょう。
同じ質問が何度もくるようでしたら、多くのライターが迷う箇所ということですので、あらかじめ決まりごととして定めます。
また、ディレクターから複数のライターに同じことを指摘するようでしたら、それらもエクセルにまとめて、決まりごととして定めます。
そのようにしていくと決まりごとが溜まっていき、それらをまとめたものがレギュレーションになります。
自分自身のディレクション業務をラクにするためにもしっかりしたレギュレーションを作成することが望ましいでしょう。
レギュレーションをガチガチに固めずライターに自由度を持たせる
レギュレーションを作成するといっても、決まり事が多すぎるとライターも記事が書きにくいと感じてしまいます。
特に、含めるキーワードの出現率や記事の文章一致率(コピペ率)などの決まりを厳しくすると、そこばかりに気を取られすぎてしまい、記事全体で不自然な内容にまとまりがちです。
決まりは定めつつも、ライターにある程度自由度を持たせて執筆してもらった方が、読みやすい文章に仕上がる傾向があります。
ディレクターの心構えとしては「木を見て森を見ず」にならないように、決まりと自由度のバランス感覚も気にするようにしましょう。
最初に依頼した内容を途中で変更しない
ライターに最初に依頼した内容や要件を途中で変更しないようにしましょう。
ディレクターはプロジェクトを進める中で、ライターに限らず多くのクリエイターに仕事を依頼することもあると思いますが、デザイナー、エンジニアなどに依頼する際も、最初の要件を途中で変更しないようにします。
ライターは、最初に依頼をもらった内容で納期までの日程から逆算して制作物完成までのスケジュールを組み立てて見積もりを出します。
ライターとしても、途中でトラブルが起きた際のことを考えてスケジュールを算出しますが、それでも依頼内容が変わるとなると、その内容に合わせて完成までのスケジュールを組み立て直さなければなりません。
途中で変更するとなればすでに作業を進めていると思いますが、途中まで進めている分の費用が発生しないとなると、ライターにとってはその分の作業コストは赤字です。
途中変更でモチベーションは下がり、納品までの時間もかかってしまい、ライターにとってもディレクターにとっても良いことはありません。
基本的には、発注内容の変更をしたい場合は追加で費用をお支払いして対応してもらうことが望ましいでしょう。
一方で、ディレクターの立場としても「この要素を要件に入れるのを忘れた」「やっぱりターゲットが違うかもしれない」などと、発注した後に課題が見えることも多々あるので、「やっぱりこうしてほしい!」と内容を変更したくなる気持ちも分かります。
ですがこのような見落としやケアレスミスも、基本的にはディレクターの責任として捉えるようにして、ディレクターの範囲で修正対応するつもりでいることが望ましいです。
もちろん、誠意を込めてライターに「追加してほしい」「どうしても変更したい」と懇願すれば対応してくれる方も多いですが、さも当たり前のように振る舞うのは決してやめましょう。
求める品質では納品されない前提で準備する
誤解を恐れずにいうと、求める品質で記事を納品してくれるライターは少なく、特にアウトソーシングでの依頼は求める品質で納品されることは無いと思った方が良いでしょう。
また、文字単価、記事単価をアップすればそれに比例して品質も良くなるかというと必ずしもそうではなく、たとえ相場よりも高い金額で依頼しても質の悪い記事が納品されることもあります。
もちろん、金額以上に上質な記事を納品してくれるライターもいるので、このような言及をするのは心苦しいですが、ディレクターの心構えとしては、求める品質では納品されない前提で準備しておく方が、円滑にプロジェクトを進めることができます。
求める品質で記事が納品されなかったときのパターンは、
- 記事としては問題無いけど内容が求めていたものと違う
- 構成力、文章力がなくて記事としてまとまっていない
という2つのパターンがあります。
前者①の場合はライターの能力はあるけど依頼内容がうまく伝わっていないことが原因で生じるズレです。この場合はディレクターは依頼内容をしっかりと伝えたつもりでも結果的に伝わっていなかったということですので、過不足なく発注できるようにディレクションを磨く必要があります。
具体的には、ターゲットとする読者の認識にズレがあったり、記事およびサイトの目的が共有できていないことによる認識のズレがあったりします。
ターゲットや目的の認識はディレクター自身が明確に把握していないと上手く依頼ができないので、ディレクターの心構えとしては、単に記事発注のやりとりをするだけだと思わずに、ビジネスにおけるプロジェクトの位置付けと制作する記事の役割を理解するように心掛けると、よりディレクションをしやすくなります。
後者②の場合はライターに能力がないことが原因で生じるズレです。この場合はライター採用の段階で不備があったということですので、応募時の限られた情報の中から判断して文章力のあるライターを採用できるようにしましょう。
ライターを教育・育成するという意識を持ちすぎない
自分がどのようなポジションでディレクションを行っているかによって、ライターを育成するかどうかを判断しますが、ライターを育成する意識をべき立場は
- 社員のライターを抱えている
- ライター育成スクールのメンバーとしてディレクターをやっている
場合で、それ以外の立場であればライターを教育するという意識はあまり必要ありません。
ライターを育成するということは、育成するためにコストがかかっていることになります。それは金銭的なコストでは見えないかもしれませんが、育成のためには、質問に回答をしたり指導したりする時間的コストが発生しています。
そのような教育にコストをかけるのは、ベンチャー企業やフリーランスにとっては非効率的で費用対効果は悪いと言わざるを得ません。
また、ライターは業務委託契約で単発で依頼するケースが多いので、社員と違ってこれから先も継続して案件を請けてくれるとは限りませんし、一生懸命育成してある程度育ったところで独立したり、より高単価の案件に移っていくことも稀ではありません。
そのようなことがある以上は、教育にコストを掛けるのはやはり費用対効果が低くなってしまいます。
Twitterを見ていると「初心者のときから一生懸命教えたのに、書けるようになったら独立した」という趣旨の嘆きを見かけることも多々あります。
ライターの中には「この会社に育ててもらったから」と恩を感じてずっと継続してくれる方もいらっしゃいますが、基本的には期待しない方が望ましいです。
【最後に】長い目で見たときにどちらがいいか?
ライターとやりとりするときの心構えと気をつけることをもう一度おさらいすると、
- 仕事内容に見合った単価になっているか確認する
- レギュレーションを用意して執筆前に確認してもらう
- レギュレーションをガチガチに固めずライターに自由度を持たせる
- 最初に依頼した内容を途中で変更しない
- 求める品質では納品されない前提で準備する
- ライターを教育・育成するという意識を持ちすぎない
この6項目になります。目先の利益しか考えないディレクションは、そのしわ寄せが後々自分に返ってきて、ディレクターの仕事が増えるばかりです。
今回の内容は大きく括れば「いかに準備を整えるか」に集約される話です。
ライターとのやりとりをうまくやっていいお付き合いの中で仕事を進めていくためには、行き当たりバッタリのやりとりではなく先の出来事を想定した準備が不可欠です。
最初からうまくいくことはないと思いますし、今回お伝えしたような事例をすでに経験してライターの対応に困っていた方もいるかもしれませんが、それらの経験を次に生かすことでディレクション力も高まっていきます。