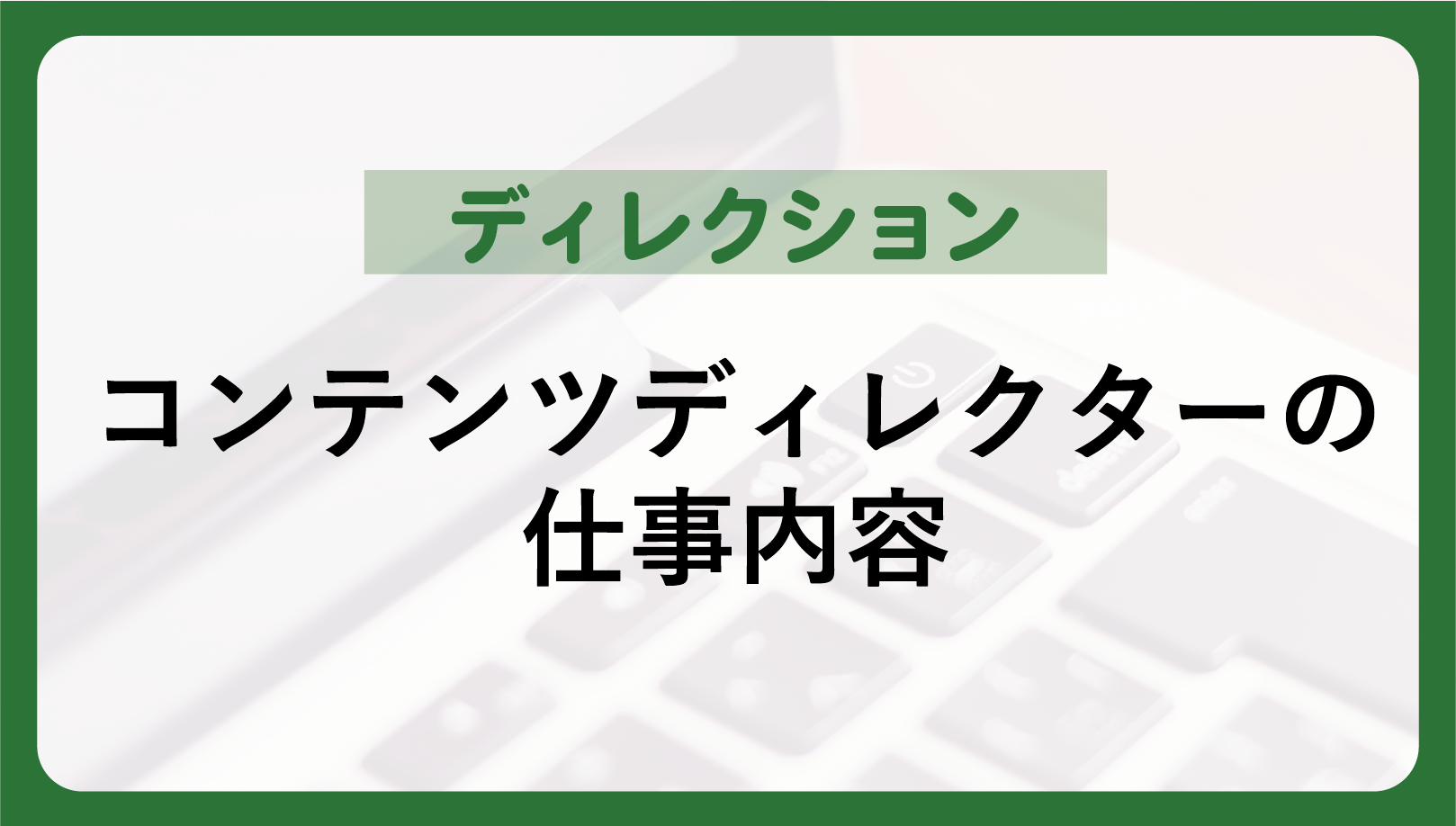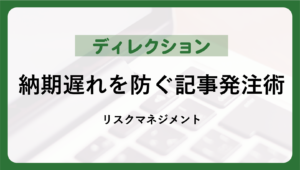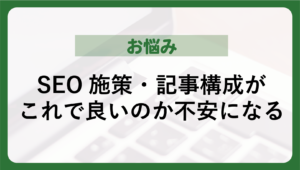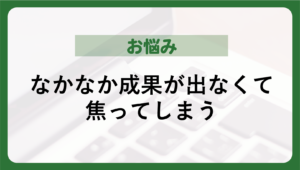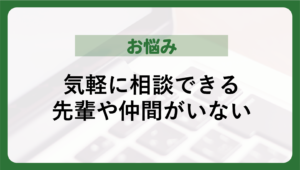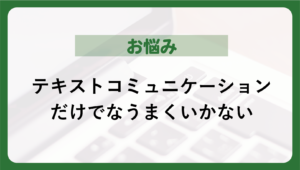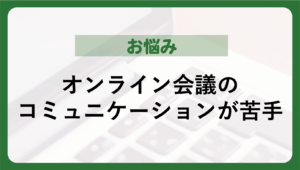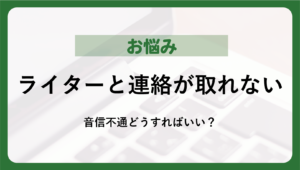ディレカレのオンライン講座では、社内に先輩がいないディレクター初心者やひとりウェブ担当者、ひとりマーケターが、何かとトラブルが多いWebマーケティングの実務に役立つ知識やノウハウをお伝えします。
Webディレクターにはさまざまな役割が与えられており、会社によって、もっというと事業によって仕事内容が異なる場合があります。
その大きな理由は、世の中には一つとして同じ事業は存在しておらず、リソースも事業によって異なるからです。
そのため、Webディレクターの役割を明確に定義することは難しいですが、当サイトでは以下のようにWebディレクターを定義しています。
プロジェクトの推進者として、Webマーケティングに必要なコンテンツの品質や完成度に責任を持ち、制作の進行管理を行う仕事。
その中でもコンテンツディレクターは、ここで定義した“Webマーケティングに必要なコンテンツ”のうち、記事コンテンツの制作ディレクションを行います。
記事制作ディレクターと呼ばれることもありますが、ディレカレでは統一してコンテンツディレクターと呼んでいます。
さて、記事制作ディレクターが管理する記事コンテンツは、自社のプロジェクトで使われるか、もしくはクライアントに納品する形になると思いますが、この「記事」は最終的にどこかのサイトに投稿されることになります。
ということは、そのサイトのデザインやシステム関係の制作管理をしているディレクターが他に存在しているはずで、その方はディレクター専任としてではなくプロジェクトを統括するプロデューサーが兼任していることもあります。
Web業界では、このようにより上位の領域を管理するフェーズのことを「上流領域」と呼ぶことがありますので、覚えておきましょう。
ちなみに、コンテンツディレクターは、ライターにとっての上流領域になります。
プロジェクトの指示系統の流れを川の流れに見立てて、上流から下流に流れていく様子を表現したもので、多くの場合は上流領域を上司が担います。
同じ企業の中では自分の上司が上流領域を担うケースが多いので、上下の関係でも違和感がなかったのですが、近年はディレクターをはじめ、ライターなどのコンテンツ制作スタッフを業務委託するケースが多くなり、この上流、下流の考え方が見直されつつあります。
「あくまで対等な関係でお互いをリスペクトして仕事をしていこう」
という意識でもあるので素晴らしいことですが、便宜上、上流領域と言った方がわかりやすいので、当サイトでは上流領域と表現する箇所がありますがご了承いただければ幸いです。
ここからは、コンテンツディレクターの仕事内容を見ていきましょう。
1. ディレクターに求められている仕事の範囲を把握する
今回のプロジェクトにおいてディレクターに求められることを初めにしっかりと把握しましょう。
自社メディアの場合は上司に、クライアント案件であれば依頼者に確認を取ります。
このときに、プロジェクトの全体像、ビジョン、KIPなどの数値目標も合わせて共有してもらうと、今回任されているディレクションの位置付けを認識できて、コンテンツの見通しを立てやすくなります。
ここで仕事の範囲を確認することで、自分が責任を持って取り組む範囲が明確になり、このあとのスケジュールを組みやすくなります。
逆に、仕事の範囲を確認しないまま進めてしまうと、想定外の業務を求められたときにその場しのぎの対応をしなければならず、自分のキャパ以上にタスクが増えてしまう可能性があります。
特にクライアントからの依頼には注意が必要で、自分が思っている業務範囲とクライアントが思っている業務範囲に乖離が生じることが多々あります。
例えば、自分は記事をデータで納品するまでが依頼の範囲だと思っていたけれど、クライアントは記事をサイトに投稿するまでを依頼したつもりだとします。
この認識の違いに気づくのが契約して業務が始まったあとの場合、今から予算をもらうこともできないため誰かに依頼することもできず、泣く泣くディレクターが無報酬で作業しなければならない、ということにもなりかねません。
その他、アイキャッチ画像、図表、記事内画像などの制作物も記事制作の範囲として求められることもあります。
追加作業分の報酬をしっかりと頂ければ良いですが、見積もりの段階で想定していた業務を超える作業は、当然赤字になってしまいます。
初心者ディレクターの場合は、あらかじめ想定できないタスクがあるかもしれませんが、できる限り初めに仕事の範囲を把握するようにしましょう。
2. 予算と必要な記事コンテンツの数を把握する
プロジェクトの中で記事制作に使える予算と、必要な記事コンテンツの数を把握しましょう。
予算に対して必要な記事コンテンツの数があまりにも多く、業務の達成が現実的ではない場合は、予算と記事数の調整が必要になります。
例えば、毎月の予算が30万円で、1記事の単価の基準を1万円にするとしたら、1ヶ月に用意できる記事数は30本になります。
これを「毎月60本の記事を投稿したい」という場合、予算を倍にするか、記事単価を半分にするか、はたまた毎月の目標投稿数を減らすか、いずれかの調整が必要です。
これから始まるプロジェクトは当然まだ成果が出ていない状態なので、成果が見えないところの予算をいきなり倍にすることは現実的ではないことが多いので、この場合は記事単価を半分にする方で調整をしていきます。
このような調整の仕方は案件ごとに異なるので正解はありませんが、こういった調整を行うのもディレクターの役割になるので覚えておきましょう。
3. ライティングチームを編成する
予算と必要な記事数が大体決まったら、それを実行するためのライティングチームを編成します。
既にライターが集まっていて、そのライターたちをまとめて欲しいという要望でディレクターを依頼されることもありますが、ここでは、新規でライターを集める流れを解説します。
ライターの募集
まずはライターを募集するところから始めます。
多くの場合はフリーランスのライターを募集してチームを編成しますが、募集方法は「クラウドソーシングのプラットフォーム」で行われます。
大手のプラットフォームは
- ランサーズ
- クラウドワークス
この2社でほとんど事が足ります。
他にも
- ココナラ
- シュフティ
などのプラットフォームがありますので、チェックしてみてください。
募集するときには、依頼内容が明確になっている募集文を用意します。記事数/文字数、報酬額、納期など、この案件に応募してくれるライターにわかりやすいように募集文を作成しましょう。
また、募集の方法としては、テストライティングの募集を行うパターンと、いきなり本案件のライターを募集するパターンの2つあります。
ライターの採用
応募していただいたライターの中から、実際に依頼するライターを選定して採用します。
ライターを採用するときには、ライターの実績やポートフォリオをチェックして、この案件にふさわしいライターかどうか判断しますが、この採用活動がディレクターの仕事の中でも重要な仕事になります。
ディレクターとしては、記事の原稿を作成していただくライターには、出来るだけ品質の良い記事を納品してもらいたいと思うはず。
まだ正式に記事を発注していない段階で、ライターの実力を判断するに足る情報は限られているので、採用活動はけっこう難しいフェーズです。
ごく一般的に考えると、経験年数が長くて、執筆本数の実績が多いライターは実力があると判断できると思いますが、それだけで判断するのは少し危険。
本数の実績が多くても質が悪いこともあるので実際に書いた記事をチェックしたり、そもそもこの案件と相性が合うかどうかをチェックしたり、さまざまな角度から判断して採用するように心がけましょう。
また、ライターは複数名採用することをおすすめします。毎月の必要記事数にもよりますが、毎月10本程度の少ない記事数でも最低2人は採用しましょう。
理由は、仮に1人のライターが何らかのトラブルでいなくなってしまっても、もう1人いればプロジェクトを止めることなく進捗する事ができるから。
1人のライターだけに依頼するのはリスクだと考えて、ライターのマネジメントを行うのもディレクターの仕事です。
いいライターは逃さないように!
ディレクターにとってライターの採用活動は重要な業務ということは、その分作業の負担も大きくなります。ですので、質の良い記事を書いてくれて自分との相性も合ういいライターは出来るだけ逃さないように!長く継続していただけるようにお付き合いをしていきます。
何名かライターを採用するうちに、「この人はずっとお願いしたいライターだ」と思う人と、「この人はこの記事までで終わりだな」と思う人が出てきます。
継続しない場合は新たにライターを採用するという流れの繰り返しを経て、いいライターが集まるライティングチームが出来上がります。
ですので、いいライターに出会ったら出来るだけ長く継続してもらえるように手厚くサポートをして抱え込みたいところ。
手厚いサポートとは、
- 報酬を上げる
- 丁寧なフィードバックを送る
- SEOの知識などを教える
など、ライターに喜んでもらえることを行い、ライターからみて優良案件だと思ってもらえるように対応しましょう。
4. コンテンツ制作をライターに発注する
ライターに発注する
ライターに記事を発注するときは、「どんな記事を書いて欲しいか」を出来るだけ具体的に伝えてください。
この伝え方次第で納品される記事の内容や質が大きく変わってしまいます。
熟練のライターを採用したとしても、発注の仕方が悪ければいい記事は上がってきませんし、逆に初心者ライターでもわかりやすい発注をすれば問題ないレベルで記事が上がってきます。
よくSNSで「記事の質が悪かった」というディレクターの嘆きを見る事がありますが、その原因はディレクターの伝え方に不備があったと言わざるを得ません。
今後、たくさんの記事を発注することになると思いますが、いい記事が上がってこなかったときの原因はディレクターにあるというマインドセットで取り組んでください。
このマインドセットで取り組んでいれば、必ず優秀なライティングチームを編成できるでしょう。
では、具体的に何を伝えれば良いかというと、
記事の内容に関しては、
- テーマ(キーワード)
- 記事構成
レギュレーションと言われる規定、規則などに関しては、
- 記事執筆に際しての注意事項
- コピペ判定の基準
- トンマナ、ですます調、などのサイトとしての決まりごと
これらをより具体的に、明確に伝えるようにしましょう。
ただし、明確に伝えることと、内容やレギュレーションの決まりごとを厳しくすることは別物。
レギュレーションをガチガチに固めて依頼するよりも、ある程度ライターに自由度を持たせた方がのびのびと筆が進み良い記事が仕上がりやすいこともありますので、その辺りのさじ加減もディレクターが調整していきましょう。
提出された原稿をチェックする
原稿をチェックするときの手順は、
- コピペチャックをする
- まずは全体をざっと読む
- 文章の構成に問題がないかチェックする
- 各章ごとに文章の流れと内容に問題がないかチェックする
という流れで、大きなところから先にチェックをし、その後細かいところをチェックします。
そもそも記事構成がはちゃめちゃで起承転結が整っていない記事は、いくら上から修正点を指摘しても最終的に記事がまとまることはありません。
ですので、内容の細部は後回しにして、まずは大枠の構成を確認しましょう。
また、チェックするときに見るべき項目は、
- コピペではなくオリジナルの文章で書かれているか
- 依頼したテーマに対して適切な内容が書かれているか
- 日本語として読める文章になっているか
この辺りを重点的にチェックして、追加して欲しい箇所や修正して欲しい箇所をみていきます。
修正箇所をライターにフィードバックする
記事をチェックしたらライターに修正依頼とフィードバックを送ります。
修正依頼をするときは、
- 修正して欲しい該当箇所を
- どのように修正して欲しいか
- 修正して欲しい理由
を明確にして送ります。
依頼の方法は、記事の原稿をGoogleドキュメントなどのファイルに写して、コメント機能で該当箇所に修正依頼を記載するとわかりやすいです。
修正箇所を記載した状態のコメントが残るように、ライターにフィードバックを送る前にワードファイルなどにダウンロードしておくことをおすすめします。
また、修正はできるだけ1回で済むように依頼しましょう。修正回数が多くなればなるほど、ライターの対応が雑になる傾向があります。
ディレクターの言い分として、「元々しっかりとした記事を納品してくれなかったライターが悪い、真摯に修正するべきだ」と思う気持ちもわかりますが、中には対応をしてくれないライターもいます。
ここでのディレクターの考え方としては、
「修正依頼が多くなってしまう原因がどこにあったか?」
「依頼の段階で不備があったのでは?」
というスタンスでこれまでのタスクを振り返ると、次回以降に同じことを繰り返さずに済みます。
もし、何度も修正をしなければならない場合、問題ない状態になるまでライターに修正を依頼し続けるよりも、ディレクターが巻き取って社内で修正する方が手間と工数が少なく済むこともあります。
依頼者としては未完成の状態で完了としてお金を払うのは不本意ですが、全体の流れをみたときに、ディレクター側で対応した方がプロジェクトが円滑に進むのであれば早めに区切ってしまいましょう。
このようなことが起きた時に損失が少なく済むように、複数のライターでリスクヘッジをし、少ない本数で依頼することが望ましいです。
5. クライアントにコンテンツを納品する
クライアントから記事制作を依頼されている場合は、ライターから上がってきた記事をまとめてクライアントに納品します。
そのときに、ディレクターが再度記事の校正校閲を行って、クライアント側の確認作業を出来るだけ簡素にします。発注数が多い案件の場合は校正校閲を専門に行う編集者をチームに加えることもあります。
クライアントは基本的には上がってきた記事をそのままサイトに投稿したいと思っているので、それを踏まえてディレクションを行いましょう。
また、品質の維持はもちろんですが、納期は確実に守るようにしましょう。納期遅れはクライアントの信用を損ない、今後の取引にも悪影響を与えてしまいますし、不要な確認工数を増やしてしまいます。
ディレクターの仕事を出来るだけ増やさないためにも、納期はシビアに考えて損はありません。
ライターの納期遅れは言い訳にならない
クライアントへの納品が遅れてしまう原因は、
- そもそものスケジュール感を見誤った
- ライターの納期遅れ
が挙げられます。
前者は完全にディレクターの責任なので、経験を重ねていきながら余裕を持って納品できるスケジュール管理のスキルを身につけましょう。一度でもプロジェクトを完了させた経験があれば、その経験をもとに見積もって段取りを組むことができるようになります。
一方後者の「ライターの納期遅れ」については、もちろんライターに落ち度があるのですが、それはクライアントには全く関係のない話ですので、クライアントへの納品遅れの言い訳にはなりません。
クライアントからしたら「そのライターさんを起用したあなたが悪いですよね」と考えるのは当たり前の話です。
ディレクターとしては悔しい気持ちもありますが、ライターのリクルーティングとマネジメントもディレクターの仕事ですので、その認識を持った上でディレクションに取り組みましょう。
納品した記事が「SEOの効果がない」と言われたら
クライアントからSEOの効果を期待して記事制作を依頼されたとして、SEOライティングで制作した記事を納品したにも関わらず、SEOの効果を発揮できないことも少なくありません。
理由は、検索順位を決めているアルゴリズムは記事の内容だけをみて順位を決めているのではなく、Webサイトとそれにまつわる施策の内容を総合的に判断して順位を決めています。
そのため、記事が良くても他の要素が基準を満たしていなければ順位が上がることはなくSEOの効果を発揮できません。
納品後にトラブルにならないように、記事制作を受注する際に「SEOの効果がある」と謳って営業をするのか、「SEOの効果は保証できない」として営業をするのか、スタンスをはっきりとしておくことをおすすめします。
6. 記事をサイトに投稿する
自社案件の場合は、サイトに記事を投稿してマーケティングの効果を測っていきます。
サイトに投稿する際、特にSEOを考慮して作成している記事の場合は、検索エンジンにコンテンツを正しく認識してもらえるように、マークアップを適切に行いましょう。
ワードプレスなどのCMSを使っている場合は、タイトルや見出しのタグを付けるのが容易なので、HTMLやCSSの知識がなくてもタグ付けして投稿できるため、この記事の投稿をディレクターが行うケースも多いです。
コーディングができるようになる必要はありませんが、ワードプレスで投稿できるスキルはぜひ身につけておきましょう。
また、SEO対策においてはコンテンツの内容だけでなく記事の内部リンクの貼り方も重要です。記事の投稿や、投稿後のタグやリンクの修正などをスピーディに行うためにも、記事の投稿と投稿された記事はディレクターが管理することが望ましいです。
ちなみに、記事投稿をライターが行うケースもあります。ワードプレスのような個人でも一般的に使われているCMSの場合はライターに記事入稿までを業務範囲として依頼する業者も増えてきました。
ライターが投稿するのは問題ありませんが、その場合は不特定多数の人が投稿することになるので、見出しの付け方や引用タグの使い方、太文字や赤文字を使う頻度などをルール決めして、初めてのライターでも問題なくできるようにマニュアルを用意することをおすすめします。
7. 検索順位やアクセス状況の分析
このステップは自社メディア運営の場合に限りますが、記事を投稿した後に、その記事が読まれているか、検索順位が付いているかなどの分析を行い、施策の効果を検証していきます。
ディレクターが分析を行いそれぞれの記事の貢献度を把握することで、現場レベルで次に打つ施策を立案でき、よりユーザー視点に立ったWebマーケティングを実行できます。
得てして、SEOコンサル業者やオウンドメディアコンサル業者はデータ上の傾向だけで対策を検討しがちで、それが現場の空気感と乖離してしまうことがあります。もちろん、客観的事実としてデータを参考にするべきですが、データと現場のバランス感を損なわないように注意しましょう。
余談ですが、プロジェクトの序盤で設定するKPIはここで生きてきます。
分析をする際には何かの指標を基準にして、その指標からの差分を測ると分析結果をまとめやすくなります。
例えば、このプロジェクトで初めて記事を投稿したとします。最初にライターから上がってきた10記事を投稿したとしましょう。
1ヶ月後にそれらの記事のアクセス状況などを分析しようとしたときに、ただ漠然とデータを見ても良い結果なのか、思わしくない結果なのかを判断することができません。
そこで重要なのが、プロジェクトを実行する際に最初に設定したKPIです。
このKPIに対してどこまで達成しているのか?という視点で分析すると、これまでの施策の評価が見えてきます。
検索順位とアクセス状況は毎日確認しよう!
投稿した記事の検索順位とアクセス数などの数値は毎日チェックして、サイトがどのような状態にあるのか把握するようにしましょう。
記事を投稿し始めた最初の頃は、検索順位も付かず、アクセスも全然伸びないので、「本当にこのまま進めて大丈夫なのか?」と心配になることもあると思います。3ヶ月〜6ヶ月は目に見える成果がなかなか出ないのが一般的ですので、焦らず日々のタスクをこなしていきましょう。
毎日チェックをしていると、ちょっとしたアクセスの増減や、検索順位の変動に気付くようになってきます。
「なぜこの記事だけアクセスが集まるのか?」「なぜこのライターが書いた記事だけ検索上位表示されるのか?」などの何らかの変化や傾向が見えてきますが、その変化に気付くようになると「この記事はもっとこうした方がいいのでは?」というように仮説を立てられるようになります。
これが、毎日のチェックではなく月一程度のチェックになると、日々の小さな変化に気付くことができず、漠然と記事を投稿しているだけになってしまい、オウンドメディアを運営する意味を見失ってしまうことも。
また、経営者やサイトのオーナー、プロジェクトリーダーは、運営しているサイトがどのような成果を生んでいるのか気になっています。常にサイトの状況を把握して、「どうなっているの?」と聞かれたときにすぐに答えられるような準備もしておきましょう。
最後に
コンテンツディレクターの仕事の全体像を把握できたでしょうか?
ディレクターは「現場監督」と例えられるがあるように、PJを進捗させるためにやるべきことが多く、ディレクターの判断で現場での意思決定が必要な場面も頻繁に発生します。
ときにシビアな決断をしなければならないことがあったり、成果に対してのプレッシャーを感じたりと、精神的にハードだなと感じることもある仕事です。
その代わり、マーケティングの最前線で仕事をする経験は必ず成長に繋がりますし、振り返ったときに自分の成長も実感できるのがこの仕事の醍醐味と言えるでしょう。
また、コンテンツディレクターはWebマーケティングの上流領域を目指す方にとって登竜門となる仕事だと感じます。
Webディレクター、Webプロデューサーなどの上流領域でマーケティングをやるときにも、記事制作のディレクションをやった経験は必ず生きますし、上流領域にいったときに現場感を持っている人材は重宝されるので、ディレクターのお声がかかっている方は是非チャレンジしていただきたいと思います。
この記事は全体像を解説する記事でしたので深いところまで触れませんでしたが、各タスクごとの仕事のやり方やノウハウも解説していますので、コンテンツディレクターに必要な知識を徹底的に身につけていただければと思います。