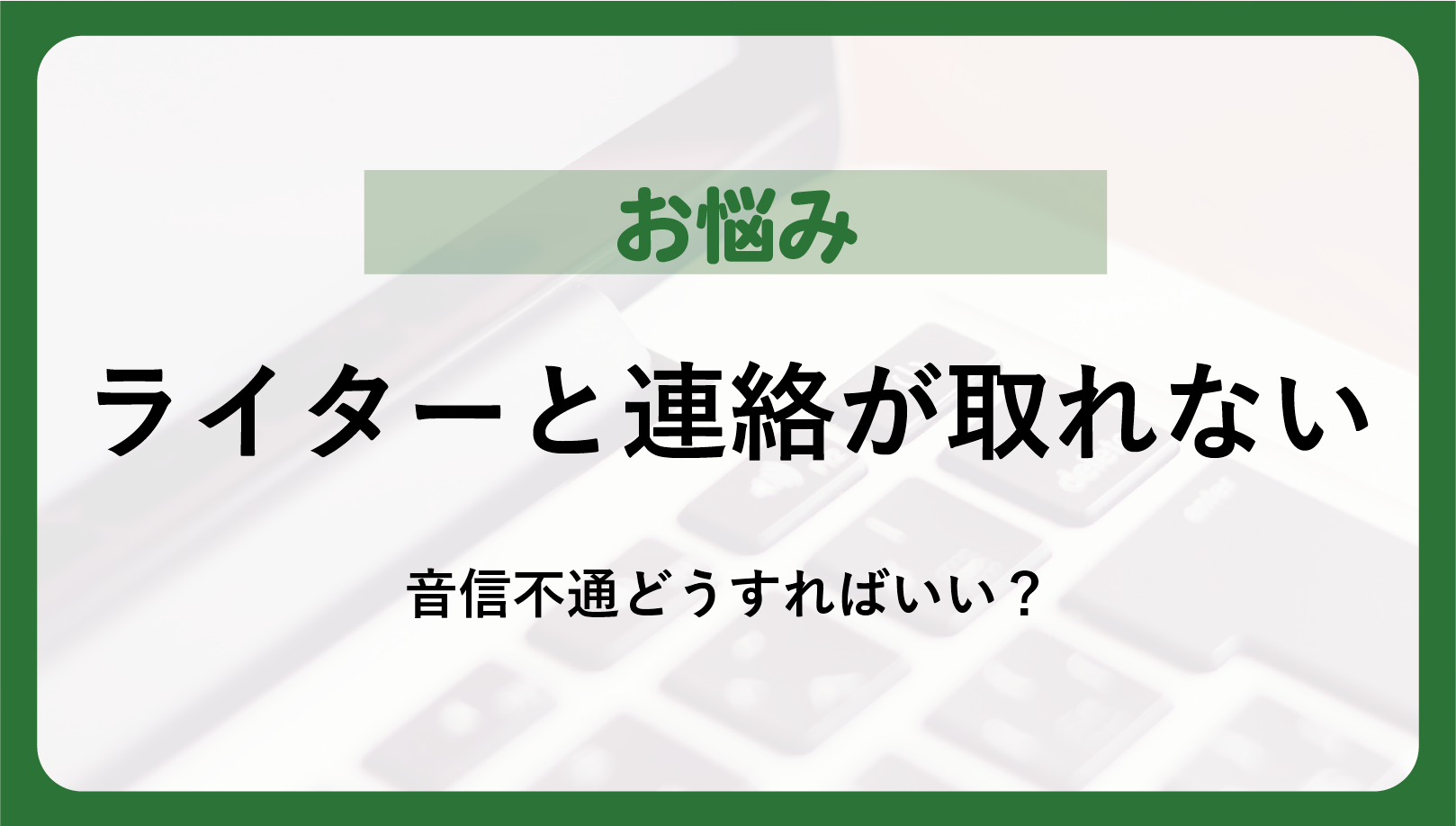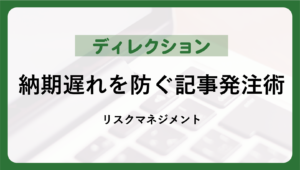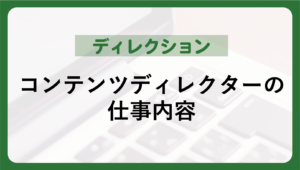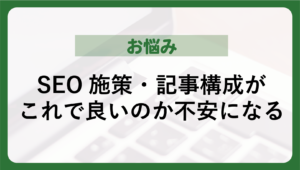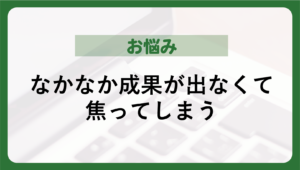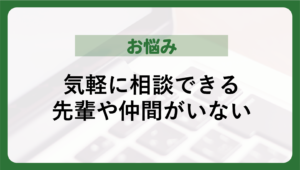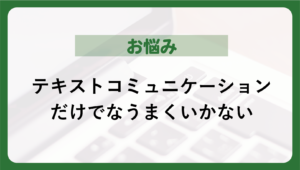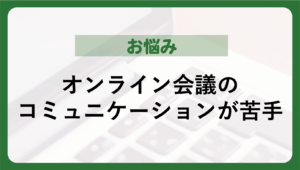ライターと連絡が取れなくなり、記事を納品してもらえないことも、コンテンツディレクションをしている中ではよくあるトラブルです。
Webライターは誰でもできる仕事として認知が広がっており、実際に参入障壁が低いことから気軽に始める人もたくさんいます。
一方で、気軽に始められるために責任感を軽視して、簡単に仕事を放棄したり、いわゆる「バックレ」をする人も一定数いるので、ディレクターとしては注意をしなければなりません。
もし、ライターと連絡が取れなくなってしまったら、ほとんどの場合は泣き寝入りで終わってしまい、ディレクターの負担が大きくなるばかりです。
重要なのは、ライターと連絡が取れなくなることも想定したディレクションをすることですので、どういう心算でディレクションをすれば良いか、解説していきます。
ライターと連絡が取れなくなったらどうすればいい?
コンテンツ制作を依頼したライターと連絡が取れなくなった場合、ほとんどはそのまま連絡が取れずどうすることもできない状態になってしまいます。
発注者としては心底腹立たしいですが、連絡が取れなくなったライターに対してはどうすることもできません。
諦めて新しいライターを探したり、不足分の記事を他のライターに回したり、プロジェクトを回していくことを優先して、次に切り替えていきましょう。
金銭的な損失はあるの?
ランサーズやクラウドワークスなどのプラットフォームでライターに依頼している場合は、プラットフォームの規約で一定期間の連絡が取れない際はキャンセル扱いになり、仮払いしたお金は戻ってくる仕組みになっているので、損失は限りなく少なく済みます。
ライターと直接契約をしている場合も、基本的には報酬は後払いになるので、連絡が取れなくなりコンテンツが納品されなければ金銭的な損失はありません。
金銭的な損失は少なく済みますが、別のクライアントにコンテンツを納品しなければならない場合は、納期までにコンテンツが揃わず、信用を損ねてしまうことがあります。もしかすると、金銭的な損失よりも信用を損ねる方が損失は大きいかもしれませんね。
ライターに損害賠償を請求できるの?
ライターと連絡が取れなくなることにより、クライアントとの契約が解消されて本来得るはずだった売上に影響がでるなど、実損が発生した場合は、ライターに対して損害賠償を請求できるケースもあります。
ただし、SNSを通じてライターに依頼していて契約書を交わしてない場合などは、損害賠償請求に至らないこともあると思います。
弁護士に依頼する費用や示談成立までの労力を考えると、ここで損害賠償まで突き詰めずに、諦めて終わりにする人も多いようです。
「ライターと連絡が取れなくなるリスク」を想定して発注する
冒頭でも触れましたが、WebライターやWebのアウトソーシング界隈では最低限のマナーやモラルを守れない人が一定数います。
クラウドソーシングのプラットフォームが出現し始めた黎明期に比べれば、しっかりしている人が増えた印象ですが、参入障壁が低い分、ファジーな人が多いのも事実。
ディレクターとしては、そのような業界だと認識した上で「ライターと連絡が取れなくなるリスク」を想定してマネジメントをすることで、自分が受けるダメージを少なくすることができます。
ここからはコンテンツディレクターができるリスクマネジメントについて解説していきます。
直接契約の場合は必ず契約書を交わす
直接契約をする場合は必ず契約書を交わすようにしましょう。契約書を交わさないことがライターの意識低下にも繋がりますし、契約書を交わすことで双方の気持ちが引き締まり責任感も生まれます。
業務委託契約に関わる契約書のフォーマットはネットを探せば手軽に入手することもできますし、顧問弁護士がいる会社でしたら、まず弁護士に相談してみてください。
後払いを徹底する
金銭的な損失を出さないためには、報酬の支払いを後払いにするように徹底しましょう。ライターから納品されたコンテンツの数に応じて月末締め翌月末払いとしている企業が多いです。
ただし、依頼するコンテンツの数が多かったり、中長期で業務を行う場合は前払いになることや、一部を前金として振り込むこともあります。
また、コンテンツだけでなくサイト制作も含めたメディア構築を依頼する場合も前払いになるケースがあります。
一概には言えませんが、肌感覚として100万円を超える依頼になると一部前払いとなるケースが多い印象です。
クリエイター側としても、大きな報酬額になる場合は振り込みされないリスクを避けたいと考えるので、前払いや一部前金にしたい気持ちもわかります。基本的には双方の協議の上、お互いに気持ちよく取引ができるように進めていきましょう。
小単位の発注で損失を減らす
一度の発注数や発注金額が大きいと、その分ライターと連絡が取れなくなったときの損失も大きくなります。
また、一度の発注数が大きいと、ライターと連絡が取れなくなったときのリカバリーも大変になってしまうので、その後のリスクも考慮した上で、発注は小単位で行った方が無難です。
特にディレクターとしてまだ慣れていないときは、一度の発注数は多くても5本程度が望ましいでしょう。やりとりの手間は発生しますが、できれば1本ずつの発注にすることでリスクを限りなく抑えることができます。
何度も同じライターと取引をしていくうちに、両者の間に信頼関係が構築されるので、関係が構築された頃に発注数を増やしていく形が理想です。
一人のライターに依存しない
一人のライターに依存しないこともリスクマネジメントになります。
ディレクターとしてはやりとりする人数を減らした方がマネジメントは楽になりますが、そのライターと急に連絡が取れなくなった場合、別のライターを採用するところから始まり、メディアに合う記事を書いてもらうように教育をしなければなりません。
その間はプロジェクトが止まってしまいますが、動いていない間はビジネスとしては損失になってしまいます。
ですが、ライターを複数人に分散することで、仮に一人のライターと連絡が取れなくなったとしてもコンテンツの投稿がゼロになることはありませんし、場合によっては他のライターに多めに記事を書いてもらうなどの調整も可能です。
毎月10本のコンテンツを制作する予定でしたら、2〜3名のライターで回していく形で検討しましょう。
プラットフォームを使ってリスクを減らす
プラットフォームは、発注者と受注者を繋ぐ役割ですので、直接的な監視力はありませんが、プラットフォームを利用することで評価制度があったり、仮払いの制度があったりと、間接的な監視力があるので、リスクを減らすことができます。
特に評価制度があることによって、その評価によっては今後の仕事に影響が及ばないようにしっかり仕事をしようという気持ちになります。
この気持ちがあるかどうかだけでも責任感が変わってくるので、評価制度だけでもプラットフォームを使うメリットがあると言えるでしょう。
一方で、誰でも気軽にプラットフォームに登録できるので、モラルがないライターも多く所属しているのも実情です。
特に文字単価が1円を下回る案件では初心者や経験が少ないライターも応募しやすいので、モラルがないライターに当たる確率も高くなりがちです。
ですので、プラットフォームを使う場合はライターと連絡が取れなくなっても「こんなもんだ」と割り切って、どんどん入れ替えていくつもりでいるのがちょうど良いかもしれません。
そのように入れ替わりを繰り返すうちに、真面目でやりとりしやすいコンテンツ制作チームが出来上がっていきます。