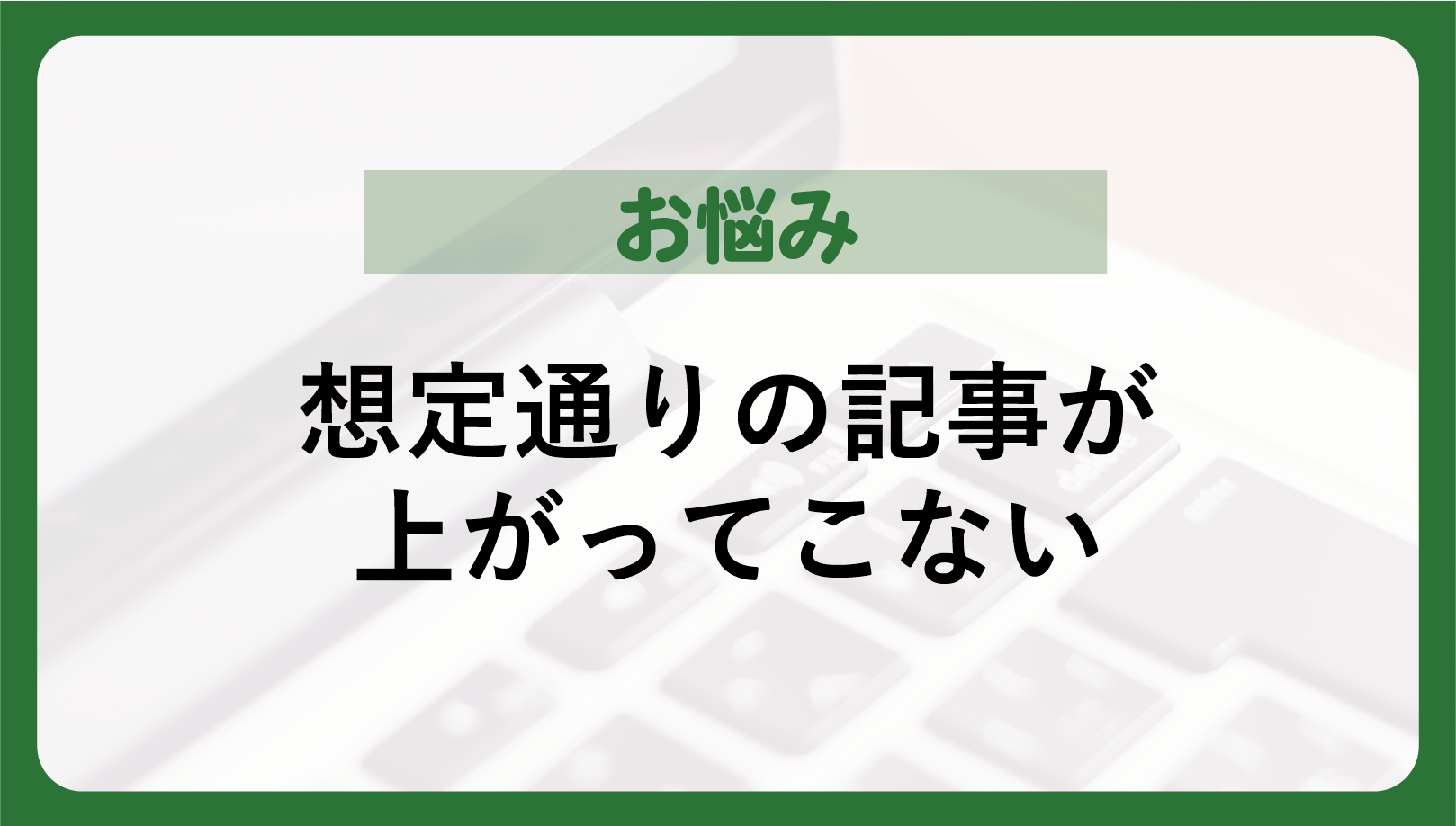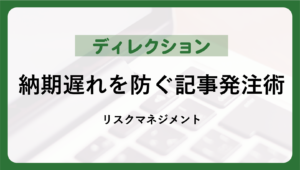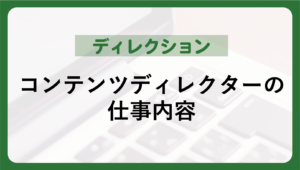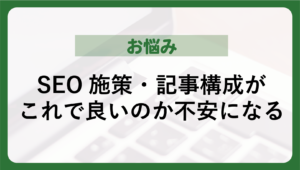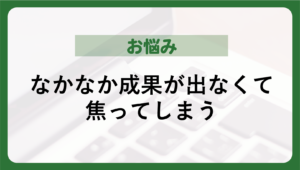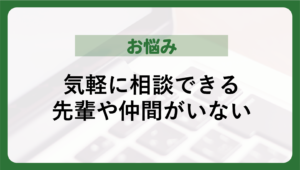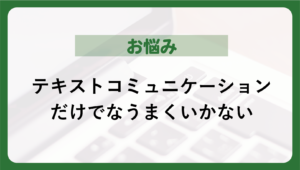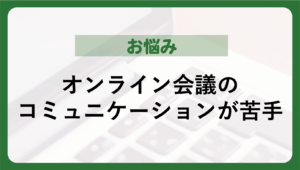まずは理想通りではない箇所を明確にする
納品されたコンテンツを読んで「想定していた内容と違う」と感じたときに、最初にやることは、どのあたりが想定とズレていて、理想と離れているのか明確にすることです。
一概に「理想通りじゃない」といっても、内容によって修正ポイントが異なるので、
- どこに違和感があるのか
- 説明不足の箇所があるか
など、理想と離れている箇所を言語化できるレベルまで詳細に分析してください。
それにより“どのプロセスを改善すれば理想通りのコンテンツに近づくか”が見えてきて、的確に修正依頼を出すことができます。
違和感のある箇所として以下の4つのポイントをチェックしてみてください。
- 記事構成
- 文章自体
- 内容自体
- 情報ソース
それぞれのポイントを見ていきましょう。
記事構成
記事構成が決まればコンテンツ制作の8割が完了すると言っても過言ではないぐらい、記事構成の重要度は非常に高いです。
そのため、構成が悪いと全体的に何を言っているのかわからない文章になってしまい、全く内容が入ってこなくなります。
各項目ごとの内容は良いことが書いてあったとしても、提供する順番が悪いとせっかくの内容が台無しになることも。
ですので、もし納品されたコンテンツに違和感があったとしたら、全体の記事構成に問題がないか俯瞰してチェックしてみましょう。
対処法
文章自体
Webライターの場合、完全にオリジナルのコンテンツよりもネット上にある情報をリサーチしてまとめるスタイルのコンテンツを作成することが多いと思います。
いわゆるSEOライティングと呼ばれる書き方は、検索上位のページをリサーチして情報をまとめる書き方になります。
このように、ネット上に情報があるときの書き方で、文章自体が読みにくかったり違和感がある場合は、ライターに“情報をまとめて体裁を整える能力が足りない”ことが考えられます。
前後の文章がチグハグになっていたり、ダラダラと間伸びした冗長表現になっていたりする場合は、ライターの基本的なライティングスキルに関わるので、修正依頼を出したとしても丁寧にまとめることができません。
不本意かもしれませんが、修正が決まらずに差し戻しを繰り返すよりも、ディレクターが巻き取って校正を行った方が手間も少なく完了します。
ちなみに、納品されたコンテンツが読みにくい文章だったとしても、ディレクターは
内容をチェックしなければならないので頑張って最後まで読み進めますが、これが頑張って読まなくても良い読者の場合は、読みにくいと感じた瞬間にページから離脱してしまいます。
ディレクター感覚の「一生懸命読めばなんとか読めるか」は読者には通用しないので、ディレクターも読者視点を忘れないように意識しましょう。
対処法
内容自体
記事構成も文章も問題ないけれど、コンテンツの内容が想定と違うこともあります。
このパターンで違和感があるときは、まずは自分が想定していた内容を言語化しましょう。違和感のまま修正依頼をしても曖昧な依頼になってしまうので、修正後も想定通りにならないこともあります。
また、内容が想定通りではないときは前提の共有がうまくできていないことが考えられます。ディレクターもライターもお互いに「〜だろう」と決めつけて、ズレが生じたまま進めてしまうと、内容もズレてしまいます。
ライターとしても「問題なく作成した」つもりでいるはずなので、決して咎めることはせずに、フィードバックを送るときも丁寧にやりとりするようにしましょう。
対処法
情報ソース
全体的に文章も内容も問題ないけれど、情報の出どころが信憑性に欠けたり、データが古かったりすると、それらが違和感になり想定と違うと感じるでしょう。
このようなケースでは、ディレクター自身が参照していたデータがあったり、ディレクターが確固たるデータを持っていたりすることで、その差分が理想との乖離になっていきます。
ディレクターが得意とするジャンルでは、ライターよりも詳しいことは多々あるため、その分ライターがリサーチした情報元に物足りなさを感じるかもしれません。
自分は当たり前と思っていたことでも一般的には専門的に感じることも多いので、フラットな視点も忘れないようにしましょう。
対処法
発注が曖昧だと理想通りのコンテンツは上がってこない
ここまで、納品されたコンテンツが理想通りではないときのチェックポイントを解説してきましたが、総じて言えることは、発注に曖昧さが残っていると理想とかけ離れてしまうということ。
コンテンツディレクターがこの曖昧さが残らないように発注内容を詰めて、丁寧に依頼をすれば、理想に近い内容でコンテンツが上がってきます。
つまり、ディレクターの力量でコンテンツのクオリティはコントロールできるということです。
まずはディレクター自身がコンテンツの役割を明確にする
発注に曖昧さを残さないためには、まずはディレクター自身が「コンテンツに求めることを明確にする」必要があります。
特にプロジェクトマネージャーとしてコンテンツディレクターをしている場合は、ビジネスの全体像を把握して「コンテンツ制作は何のために行っているのか?」そして「記事一つひとつにはどんな役割があるのか?」を理解する必要があります。
ディレクターが理解して、初めてライターに的確に依頼ができるようになり、限りなく理想に近いコンテンツを納品してもらえるようになります。
外部でコンテンツディレクターをやっている場合は、クライアントのビジネスモデルの理解なくしてコンテンツの役割を把握することはできません。
ただ、外部ディレクターの立場は客観的にビジネスを見ることができるので、社内ディレクターよりも冷静な視点で把握することができます。
クライアント自身に曖昧さがあるようでしたら、そこを指摘できるのも外部ディレクターの強みですので、そのような立場を生かしたディレクションも随時行っていきましょう。
意図を汲んで理想のコンテンツを作成してくれるライターは一握り
ディレクターの発注が曖昧だとしても、こちらの意図を汲んで的確な内容でまとめてくれる優秀なライターが稀にいますが、そのようなライターはごく一握りですので、期待しない方が無難です。
ディレクターのキャリアの序盤でそのような優秀なライターに出会うと、自分の力不足を補ってもらえるため助かるのですが、一方で、優秀なライターがいなくなったときや、別の案件を任されたときに、自分の能力が試されることになるので、大変になることも。
ライターに助けてもらうことは多々ありますが、ライターに頼らなくても一定以上のクオリティで納品してもらえるようなディレクションを心がけましょう。